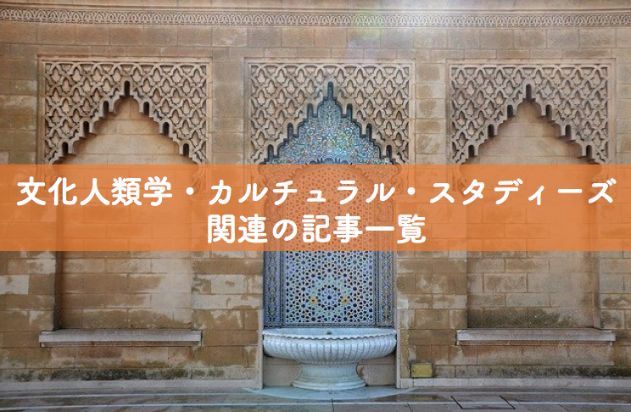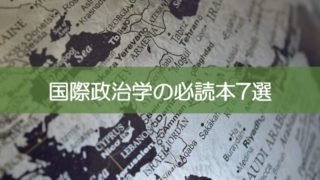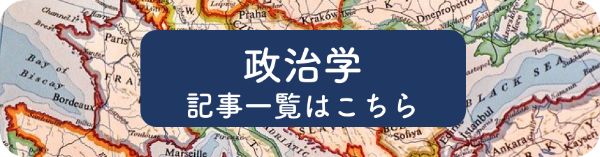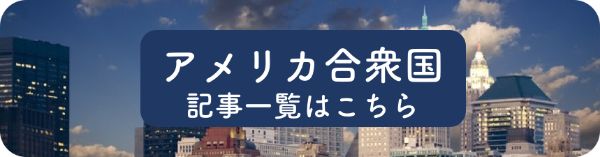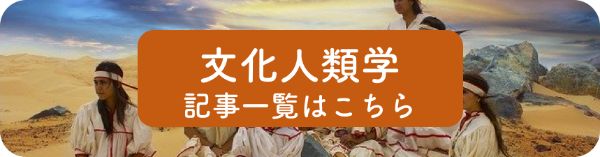このページでは、現在リベラルアーツガイドにある文化人類学・カルチュラル・スタディーズ関連の記事について分野別に紹介しています。
多数の記事がありますので、ぜひブックマーク・お気に入り登録してご活用ください。
※内容は、随時更新していきます。
文化人類学・カルチュラル・スタディーズの基本的な考え方
文化人類学・カルチュラル・スタディーズの領域を勉強する上で、「構造主義」「大衆文化」などの基本的な理論・概念の理解は必須です。
基本的なキーワードをそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
■ 文化人類学関連
文化人類学は決してメジャーな学問ではありませんが、日々、グローバル化する世界においてその重要性・必要性は増しています。まずは、そのような学問を基本的な方法論から理解してみてはいかがでしょうか?
https://liberal-arts-guide.com/field-work/
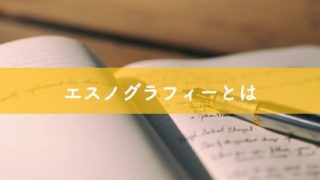
これらの方法から練り出された理論に、「機能主義」と「構造主義」があります。当然、理論はこれだけではありませんが、この二つの理論は文化人類学を学ぶ際に特に重要です。学問の歴史とともに学べる内容となっていますので、ぜひ以下の記事を参照してください。


(*構造主義を深く理解するためには、①構造言語学・②音韻論・③記号論の議論に触れる必要がある)
さらに、非西洋社会を主に対象としてきた文化人類学には、個別の特殊な概念があります。文化人類学の外部で使用されるとき、誤用されるケースがありますので、しっかり理解する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
■ カルチュラル・スタディーズ関連
「文化」が学問名になっていますが、文化人類学とカルチュラル・スタディーズは全く異なる学問分野です。両者は「仲が悪い」という状況ですが、どちらかの視点に片寄るのでなく、学際的に学ぶことが求められます。
カルチュラル・スタディーズはイギリス社会と深い関係があります。特に、第二次世界大戦後における労働者階級文化の変容に関する理解は不可欠です。そのような時代背景を理論的な基層とともに理解することが、カルチュラル・スタディーズへの第一歩です。
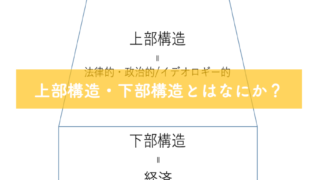
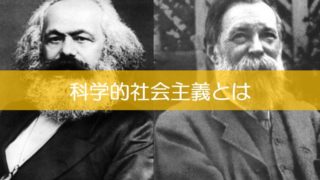
(参考:マルクス経済学の理論)
マルクス主義に加えて、カルチュラル・スタディーズの理解するために必要なのは、以下のような人文・社会科学の基礎知識です。
- 英文学の文芸批評、特にレイモンド・ウィリアムズ
- 古典的マルクス主義の批判的読解
- アルチュセールの構造主義的マルクス主義
- グラムシによるマルクス主義の解釈とヘゲモニー論
この点に関しては、次の記事でおすすめ本を紹介していますので、参考にしてください。
https://liberal-arts-guide.com/cultural-studies-books/
上述の内容と通して、ようやく「大衆文化」「サブカルチャー」といった研究に触れることができます。これら研究の基層となるのは、やはりマルクス主義の批判的読解ですので、上述の記事を参考に勉強してみてください。
さらに、マルクス主義の批判的読解は現代政治の基礎的な考え方に、クリティカルな視点をもたらします。「状況決定的(Conjunctural)な」視点は、以下のような概念にどんな再考を迫るのでしょうか?
文化人類学・カルチュラル・スタディーズに関連する社会思想
文化人類学・カルチュラル・スタディーズでは、数多くの社会思想とそれらの関係性を理解する必要があります。
特に、重要な思想については、以下の記事で解説しています。
上述してきた記事では、必ず以下のようなキーワードが登場します。これらのキーワードは文化人類学・カルチュラル・スタディーズで語られるものが多いです。しかし、この領域に限定されたワードではないので、しっかり理解しましょう。
権力論に関していえば、フーコーの権力論を理解していることが前提で議論が進みます。フーコーの議論で、特に重要なものは以下でまとめています。
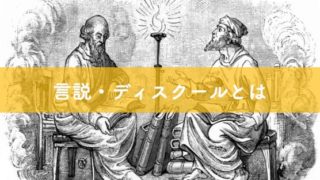
そして、人種・エスニシティ論は文化人類学・カルチュラル・スタディーズの大きなテーマです。とはいえど、人種論は莫大な蓄積のある分野ですが、以下の記事を参考にその全体像を理解してみてください。

- そもそも、人種とはなにか?→人種の基礎的な記事
- 人種とエスニシティの違いとは?→エスニシティ
- 人種と社会の関係→人種のるつぼ、ポスト人種社会論(1)と(2)、ジムクロウ法、ワンドロップ・ルール、ディアスポラ
文化人類学・カルチュラル・スタディーズの名著・人物
重要な名著と人物について、以下の記事で解説しています。
文化人類学・カルチュラル・スタディーズの領域を勉強する際に、必ず読まなければならない通過儀礼的な書物があります。文化人類学の名著には、日本人にも馴染み深いものもあるので、ぜひ以下を参考にしてください。
『菊と刀』は日本文化論として読解されがちですが、文化人類学の書物です。その点に注意して読解してみてはいかがでしょうか?
https://liberal-arts-guide.com/the-chrysanthemum-and-the-sword/
NHKの100分de名著にも選定されていた書物です。
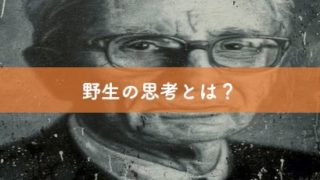
その他の名著:『西太平洋の遠洋航海者』、『ヌアー族』、『高知ビルマの政治体系』
カルチュラル・スタディーズの創設者に関してこちら:スチュワート・ホール
文化人類学が対象とする社会
文化人類学を学ぶとき、さまざまな先住民社会における個別の議論が土台となります。以下では、「ネイティブ・アメリカン」「イヌイット」「アボリジニ」の個別的なテーマを解説していますので、参考にしてください。
また、21世紀の先住民社会を考えるとき、カルチュラル・スタディーズ的な視点は大変有効です。そのため、先住民社会から両者の結節点を考えるのもよいと思います。
■ ネイティブ・アメリカンのまとめ
ネイティブ・アメリカン社会に関する基本的な議論
→ネイティブ・アメリカンの部族や歴史、居留地に関して、カジノに関して、現在の状況と未来に関して
■ イヌイットのまとめ
イヌイット社会に関する基本的な議論
→イヌイットの概論、イヌイットとエスキモーの違い、イヌイット語に関して、イヌイットの伝統的な食事に関して、イヌイットの家に関して
■ アボリジニのまとめ
アボリジニ社会に関する基本的な議論
→アボリジニの概論、アボリジニの歴史・文化・アート・言語、ディジュリドゥーに関して、アボリジニのブーメランに関して、アボリジニの現在に関して
アボリジニ史の基礎的な知識
→白豪主義
文化人類学・カルチュラル・スタディーズの勉強法
文化人類学・カルチュラル・スタディーズを学ぶ上で読んでおきたい本を、以下の記事ではまとめています。ぜひ参考にして、関連領域の本を読み漁ってください。
文化人類学のおすすめ本
→文化人類学のおすすめ6選
カルチュラル・スタディーズのおすすめ本
→カルチュラル・スタディーズのおすすめ9選
構造主義を学ぶための本
→構造主義のおすすめ本7選
フーコーを学ぶためのおすすめ入門書
→フーコー入門書をランキング形式で紹介
シャーマニズムに関するおすすめ本
→シャーマニズムを学ぶためのおすすめ7選
観光人類学のおすすめ本
→観光人類学のおすすめ本7選
ネイティブ・アメリカン社会の勉強法
→おすすめ本7選、おすすめ映画6選
イヌイット社会の勉強法
→おすすめ8選
政治学のおすすめ本
→政治学の必読書7選
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら