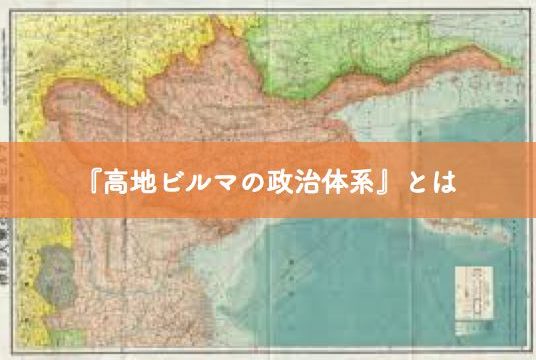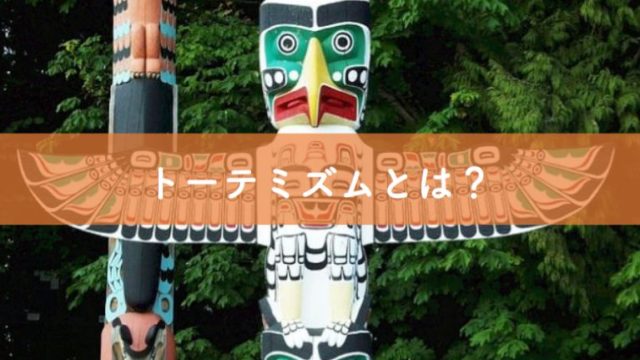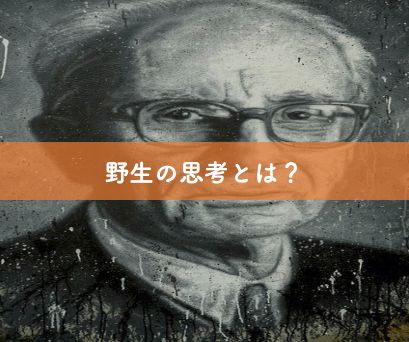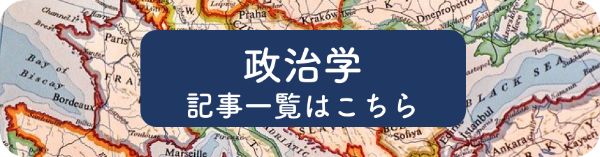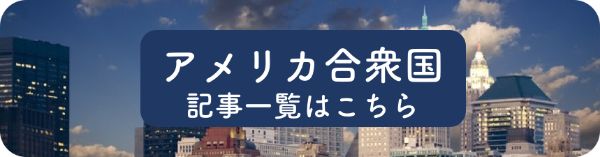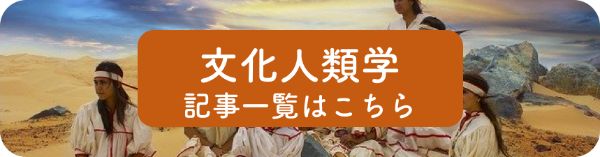タブー(taboo)とは、ポリネシア起源の用語で、「触れてはならないこと」「してはならないこと」を意味します。日本語では「禁忌」を意味します。
「タブー」というポリネシア起源の言葉を知ることは大した意味をもたないかもしれませんが、世界中のさまざま社会において「タブー」とされる行為を理解することは大事です。
なぜならば、一見規則性をもたないようにみえる世界中のタブー行為は、「穢れ」という概念から考えることで、普遍性があることがわかるからです。
そこで、この記事では、
- タブーの意味
- タブーの具体例
- タブーと穢れの議論
をそれぞれ紹介します。
あなたが読みたい箇所から、ぜひ読み進めてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:タブーとは
まず、1章ではタブーの概要となる「用語の語源」や「具体例」を紹介します。「タブーと穢れの関係」に興味のある方は、2章から読み進めてください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1: タブーの意味
再度確認しますが、タブーとは、
「触れてはならないこと」「してはならないこと」を意味するポリネシア起源の言葉
です。
「ポリネシア起源の言葉がなぜ日本でも日常的に使われているんだ?」と思った方も多いと思います。この点を理解するためには、「タブー」の歴史に触れる必要があります。
1-1-1: 「タブー」の語源
そもそも、「タブー」は、キャプテン・クックが南太平洋の航海から持ち帰ったものです。
たとえば、1784年のクック航海記には、タヒチ島の女性たちが男性たちと食事をともにせずに、特定の食物が禁じられていることが示されています。
クックに同伴した船員は、現地人を船に近づけないようにしたり、若い女性を船に閉じ込めるためにするために便利な言葉だ、と思い使用し始めたそうです2山下晋司 , 船曳建夫 『文化人類学キーワード 改訂版 』(有斐閣双書)。
いずれにせよ、現地語が人類学用語を経て日常語になった例は「シャーマン」「トーテム」とありますが、「タブー」ほど広く普及した用語は他にありません。
1-1-2: 「タブー」の広まり
では一体、なぜ「タブー」という言葉は世界的に普及したのでしょうか?端的にいうならば、19世紀のヴィクトリア朝時代のイギリス社会には、「タブー」を受容する条件が揃っていたためです。
具体的に、当時のイギリス社会は次のような状況でした。
- 宗教の合理的説明という時代的趨勢…供犠などの合理的説明のつきにくいものを一定のカテゴリーに収める努力があり、「タブー」は恰好の用語であった
- ヴィクトリア朝という時代における禁忌…性や身体に対するタブーが著しいという時代背景(ズボンをわざわざ「言いがたいもの」と言い換えるのが礼儀であった)
このように、キャプテン・クックによって持ち帰られたポリネシアの言葉は、イギリス社会を説明する便利な用語として受容されます。その後、「タブー」は19世紀初めまでにヨーロッパで広く普及していきました。
1-1-3: タブーの訳語
ちなみに、「タブー」はいくつかの訳語がありますので紹介します。
- 英語…「禁止(prohibited)」や「禁断(forbidden)」など。「タブー」はより即座に感情を表現できるため、好んで用いられた
- フィジー…「違法(unlawful)」「神聖(sacred)」「至善(superlatively good)」
- マダガスカル…「世俗(profane)」「不敬(profaned)」「不浄(polluted)」
いずれも当該社会において「タブー」に相当する言葉です。
1-2: タブーの具体例
さて、タブー視される行為は世界中に多様にあります。ここでは「宗教」と「身体」に関するタブーを紹介します。
1-2-1: 宗教に関するタブー
宗教上の食物規制は非常に有名なタブーの例です。たとえば、ヒンドゥー教、イスラム教、ユダヤ教には次のようなタブーがあります。
- ヒンドゥー教…牛は神聖視されるので、牛肉は御法度である
- イスラム教…不浄と考えられる豚肉はタブーである
- ユダヤ教…肉と乳製品を同じ食卓に出すことはできない。血のついた肉は御法度
それぞれ有名な事例ですので、聞いたことのある方が多いのではないでしょうか?ちなみに、マックランシーは『世界を食いつくす』で世界中の食に関する記述をしています。
1-2-2: 身体に関するタブーと病気や死に関するタブー
体や身体に関するタブー、病気や死に関するタブーは世界中にさまざまなものがあります。
ここでは日本の事例も含めて、いくつかのタブーを紹介します。
- 中国人の妊娠と出産…数え切れないほどの食物に関するタブーを課せられる
- 月経…生理中の女性は特定の活動から除外する社会が多い
- 日本における出産…子供が生まれてから、女性は1ヶ月食事や入浴に関するタブーがあった
- 日本における死者…49日間特定の食事を避ける習慣があった
これらの観念は当該社会における人間観を表現したものです。たとえば、日本社会から「魂」と「体」の関係で人間を捉えていることがわかると思います。
世界中のタブーをもっと知りたい方は『世界のタブー』がおすすめです。学術的な議論はいっさいないので、気軽に読めることができます。
(2025/07/17 22:18:11時点 Amazon調べ-詳細)
- タブーとは、「触れてはならないこと」「してはならないこと」を意味するポリネシア起源の言葉
- 「タブー」は、キャプテン・クックが南太平洋の航海から持ち帰ったもの
- 19世紀のヴィクトリア朝時代のイギリス社会には、「タブー」を受容する条件が揃っていた
2章:タブーと穢れ
さて、世界中にはタブー視される行為が多くありますが、それらの行為がタブー視されるのはなぜでしょうか?
結論からいえば、人類学者のダグラスやリーチは、
- 境界に位置するもの
- 分類が混じり合うところ
- 曖昧な部分
にタブーが生まれるといいます。
いきなり、要点だけいわれてもわかりにくいと思うので詳しく説明していきます。重要なのは「タブーと穢れの関係」です。
2-1: 汚いものはなにか
そもそも、「汚いもの」とは何でしょうか?「そんな当たり前のことを聞くな!」と思うかもしれませんが、「汚さ」は決して自明なものではありません3浜本満, 浜本まり子 『人類学のコモンセンス』学術図書出版社。
たとえば、次の場合はどうでしょう?
- うんちの場合…人間のうんちはとても汚い。犬のうんちよりも汚く感じ、それを靴で踏むことはもってのほかである。にもかかわらず、私たちは「汚いもの」を毎日お腹のなかに抱えている
- 食べ物の場合…食べ物は本来「きれいなもの」である。しかしケーキをうっかり服にこぼしてしまったとき、洋服についた生クリームは汚くなる。生クリームは空間を移動しただけなのに。
このような例は山ほどあります。他の社会の例を含めると、収集がつかないほど例を集めることができます。
この「穢れ」をめぐる議論で一番有名なのは、上述したイスラム教の豚肉に関するタブーです。イスラム教が豚肉を食べないのは、吐き気を催すほどきたないと考えられるからです。
事実、旧約聖書の申命記14章8節には「豚はひずめがわれているが、反芻しないため、汚いものである」と書かれています。
余計わけがわからくなったと思うかもしれませんが、安心してください。これから紹介する文化人類学者が「きたなさ」の疑問に解答しています。
2-2: 穢れの意味
「きたなさ」に関して一般理論を提示したのは、文化人類学メアリ・ダグラスとエドモンド・リーチでした。どちらの議論も汚さが「秩序」の創造と関わることを指摘しています4浜本満, 浜本まり子 『人類学のコモンセンス』学術図書出版社。
2-2-1: ダグラスの研究
まず、ダグラスはイスラム教における豚肉のタブーについて分析をしています。ダグラスは、次のような指摘をしています。
- 申命記やレビ記は神の論理にしたがった一つの秩序に一致する人間は繁栄するが、逸脱するものは災いをもたらすようなもの
- 神の秩序といっても当時の牧畜民であったユダヤ人が、理想的な世界を描いた秩序にすぎない
- 秩序を形成するためには区分が重要であり、家畜とそれ以外の獣を分けておくことは牧畜民であったユダヤ人にとって重要だった
- 家畜とそれ以外の獣の基準になったのが、「ひずめが分かれており反芻する」という基準である
つまり、牧畜民にふさわしい食べ物である家畜は「ひずめが分かれており反芻する」有蹄類である一方で、「ひずめが分かれておらず反芻しない」動物は獣として扱われます。
では、この分類に当てはまらないケースはどうすればいいのでしょうか?実は、「きたない」動物と捉えられるものは、すべて「ひずめが分かれいるが反芻しない」「反芻するがひずめがわかれていない」といった家畜とそれ以外の獣を二分する基準に一致しない動物なのです。
つまり、ウサギ、ラクダ、豚などの「きたない」とされる動物はすべてその地位がわからない境界的なケースなのです。
言い換えると、秩序による基本的な分類に当てはまらないものが「きたない」のです。「きたない」から排除されるのではなく、分類図式からこぼれ落ちるから「きたない」のです。
ダグラスの議論は『汚穢と禁忌』で読むことができます。「きたなさ」に関する議論は、この本から学ぶことができます。
(2025/07/17 22:18:12時点 Amazon調べ-詳細)
2-2-2: リーチの研究
リーチの議論もダグラスの議論と同様に、人間の秩序に関係しています。
- 環境は本来一つの連続体であるにもかかわらず、人間は多様な分離した物体からなるものとして見るように学習する
- つまり、連続体のなかに、人工的(文化的)な境界をつくりだす
- その境界に属さない曖昧なものが「穢れ」としてタブーの対象になる
たとえば、身近な例である「昼」と「夜」で考えてみてください。
- 「昼」と「夜」は光と闇のように、正反対のものとして扱われる
- しかし時間は連続的であり、昼と夜の交代は一瞬で起きるものではない
- つまり、昼と夜のどっちつかずな状態が「夕暮れ」がある
- この移行期間はロマンチックな時間、感傷的な時間、または魔性を帯びた時間と考えられてきた(夕暮れ時を「オオマガドキ」という日本習慣)
- 日本社会に以外にも、夕暮れは魔性と結びつけられる場合が多くある
このように考えると、夕暮れ時を特別な時間と考える理由は、昼と夜の境界上であること以外に必然的な理由はないのです。
時間ではなく、空間で考えても同様です。
- 村と外との分かれ目、分かれ道、十字路は多くの社会で魔物がである一番の場面である
- 駅や空港はある街や国の一部ながら外部と繋がった場所でもあるため、映画やドラマで特別な場面に使われやすい
2-3: タブーと穢れの関係
このように考えると、ダグラスとリーチは同様のことを説明しているとわかります。
つまり、
- 「きたないもの」は人間が世界秩序を構築するときに生まれる副産物である
- 私たちが境界を厳密に定めようとするとき、「きたないもの」が発生し、タブーの対象となる
といえます。
この分類の境界上が特殊にみられることは、通過儀礼の議論でも同じです。どっちつかずの状態である人間はタブーや尋常でない力をもった人物として扱われるという特徴があります。
- 「きたない」から排除されるのではなく、分類図式からこぼれ落ちるから「きたない」ものとなる
- 境界に位置するもの、分類が混じり合うところ、曖昧な部分にタブーが生まれる
3章:タブーの学び方
タブーについて理解を深めることはできたでしょうか?
まず、何よりも文化人類学という学問自体に興味をもった場合は、こちら記事を参照ください。さまざまな書籍の良い点と悪い点を解説しながら、紹介しています。
https://liberal-arts-guide.com/cultural-anthropology-books/
以下はタブーに関するおすすめ書籍です。
エドモンド・リーチ『文化とコミュニケーション』(紀伊國屋書店)
この記事で紹介したリーチの議論を学ぶことができます。タブーと穢れの関係を学びたい方、文化人類学を学びたい方におすすめです。
(2020/10/14 17:42:36時点 Amazon調べ-詳細)
浜本満・浜本まり子 (編)『人類学のコモンセンスー文化人類学入門ー』(学術図書出版社)
「けがれ−「きたなさ」の正体−」の章では、ダグラスやリーチの議論が紹介されています。この記事でも参照しています。初学者用に書かれているため読みやすいことが特徴です。
(2025/07/17 17:36:42時点 Amazon調べ-詳細)
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
この記事の内容をまとめます。
- タブーとは、「触れてはならないこと」「してはならないこと」を意味するポリネシア起源の言葉
- 「きたない」から排除されるのではなく、分類図式からこぼれ落ちるから「きたない」ものとなる
- 境界に位置するもの、分類が混じり合うところ、曖昧な部分にタブーが生まれる
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら