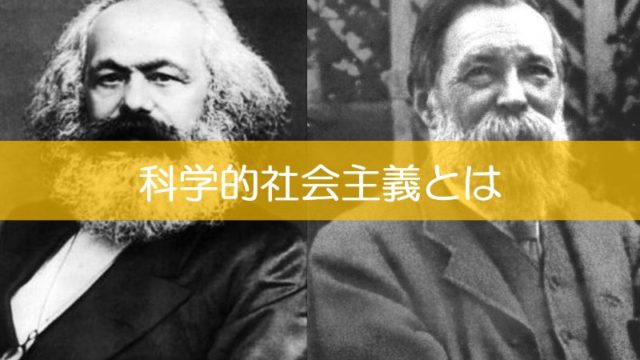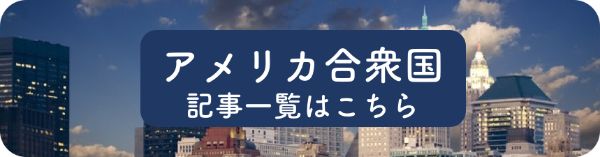サイエンス・ウォーズ(Science wars)とは、1990年代のアメリカを主な舞台に、自然科学のあり方をめぐって科学者と科学論者(自然科学を論じる人文・社会学系の研究者)のあいだで交わされた激しい論争のことです。
いわゆるソーカル事件をとおしてエスカレートした一連の論争は、自然科学の捉え方をめぐって、科学者と科学論者のあいだにきわめて大きな隔たりがあることを浮き彫りにしました。
科学者と科学論者、両者の主張にそれぞれ納得できる点があるため、どちらか一方の主張だけに耳を傾けるのではなく、まずは、両陣営でなされた議論を整理し、その理解を深めることが大切です。
そこで、この記事では、
- サイエンス・ウォーズの概要
- サイエンス・ウォーズで争われた主な論点
について解説します。
時代背景なども整理しながら分かりやすく解説するので、興味のある方はぜひご覧ください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:サイエンス・ウォーズとは
1章ではサイエンス・ウォーズの概要を確認します。その際に重要となるのは、「科学論」という学問領域です。この学問領域は、単純に科学をめぐる議論一般を意味しているわけではないため、その理解には注意が必要です。
以下では、科学論の輪郭を明らかにするところから解説を始めたいと思います。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:科学論の興隆
サイエンス・ウォーズを理解するにはまず、一般に「科学論」と呼ばれる学問領域につい知っておく必要があります。なぜならサイエンス・ウォーズとは、こういった学問の基本的な考え方や方法論を、職業科学者が痛烈に批判したことから始まったからです。
1-1-1:科学論の概要
科学論(Science studies)とは、
歴史学、社会学、哲学、心理学、経済学など人文・社会学に属する幅広い分野のアプローチを使い、科学的言説や科学的営みを再検証する学問領域のこと
です。
この学問領域は、1960年代にクーンが提出したパラダイム論を発展的に継承するかたちで出現し、1970年代にはいわゆるカルチュラル・スタディーズの展開と呼応しその理論を洗練させました(→カルチュラル・スタディーズに関してはこちらの記事)。
科学論はさらに、
- フェミニズム科学論
- 科学人類学
- 科学技術社会論(STS)
- 科学知識の社会学(SSK)
などへと細分化されます。
しかし、科学論に属する議論は総じて、科学があつかう対象のアプリオリで中立的な実在を認めず、科学的な概念や理論体系といえども、社会的・文化的条件に拘束されていると考える点で一致しています。
- 簡単に言えば、われわれの生活とは切りはされて実在し、そのために客観的だと考えられていたさまざまな自然科学の知識(たとえば「万有引力の法則」や「エネルギー保存の法則」など)でさえ、数々の社会的・文化的な先入観(とりわけ、近代西洋社会に固有の考え方)に影響されて成立しているということ
- こういった考え(一般に、社会構築主義、相対主義的認識論、反実在論などと呼ばれる)を共有した科学論は、科学的な理論体系を規定するジェンダーバイアスや政治的なかたより、あるいは西洋社会に固有の視点から記述された箇所をつぎつぎと指摘していった
こうした議論は科学を捉えるあたらしい可能性を切り拓いたとも言えますが、その一方で、自然科学の知識がいわば「文化の汚染」を受けているという考えが、「普遍的であるために神聖な」対象、つまり「自然のことわり」の探究に生涯を捧げている職業科学者の強い反発を招きます。
そしてサイエンス・ウォーズとはまさに、こうした反発を引き金に始まった激しい論争であり、科学者と科学論者は互いの主張の要旨を十分に理解しようとしないまま、感情的な相互批判を続けることになります。
ただ、科学論をめぐるここまでの説明はやや抽象的ですので、なぜ科学者がこれほどまでに激しく反発したのかを明らかにするためにも、科学論を代表する議論を具体的に確認し、その輪郭をさらに明瞭にしておきましょう。
1-1-2:ラトゥールの議論
すでに述べたように、科学論はさらにいくつかの研究領域へと細分化されます。ここではその代表格である科学人類学について確認します。科学人類学の代表的論者は、現在もフランスで哲学者、人類学者として活躍しているブルーノ・ラトゥールです。
 ブルーノ・ラトゥール (Bruno Latour 1947年〜)
ブルーノ・ラトゥール (Bruno Latour 1947年〜)
ラトゥールはアクターネットワーク理論の提唱者として有名ですが、ここでは彼の名声を一挙に高めた『実験室の生活——科学的事実の社会的構成』(本書は彼の同僚であるウールガーとの共著です)に注目します。なぜなら本書でラトゥールが提唱した学問体系こそ、科学人類学にほかならないからです。
(2025/07/12 16:25:13時点 Amazon調べ-詳細)
それでは科学人類学とはどのような学問体系でしょうか?
簡単に言えば科学人類学とは、
フィールドワークをとおして見知らぬ文化の機能体系を解き明かす文化人類学の手法をもって、あたらしい科学的な理論や知識が産み出される場所、すなわち自然科学の研究室、そして、そこではたらく科学者の生態の解明を目的とした学問
です。
そのケーススタディとしてラトゥールが分析するのは、のちにノーベル生理学・医学賞を受賞することになるロジェ・ギルマンの研究室です。
ギルマン研究室における調査
- 二年に及ぶフィールドワーク(つまり、ギルマンの研究室での滞在)をとおして得た知見をもとに、ラトゥールは、科学的な理論や知識が研究室での人間関係や研究者特有の生態と深く関連しながら生産されている様子を克明に描き出した
- ラトゥールの記述は非常に興味深く、重要な論点をいくつも提出しているが、やはりもっとも注目されるべきは、彼が自然科学の知識を、研究室での人間関係などをとおして生産されるきわめて社会的・文化的な構築物として捉えていることである
この意味で、科学人類学は科学論を代表する議論体系であるといえ、そして、現場の科学者の反感を招くことになるのは、まさにこういった考え方でした。
1-2:科学者の反発
それでは次に、科学論に対する科学者の反応を見ていきましょう。繰り返しになりますが、科学の客観性を批判的に再考する科学論は、多くの科学者にとって嫌悪の対象でしかありませんでした。
こういった状況下で刊行され、一大センセーションを巻き起こしたのが、生物学者ポール・グロスと数学者ノーマン・レーヴィットにより執筆された『高次の迷信』という著作です。
(2025/07/12 16:25:14時点 Amazon調べ-詳細)
本書でグロスとレーヴィットは、すでに紹介したラトゥールの議論などを取り上げながら科学論のあり方を痛烈に批判します。簡単言うと、以下のような内容に批判が向けられました。
科学論への批判
- 罵倒に近いかたちでなされた彼らの批判は、初等レベルの科学さえ理解していない人文・社会学系の学者が科学あり方を得意げに語っていること
- そして、こうした学者たちが、科学的言説の社会的・文化的拘束性を必要以上に強調していること
グロスとレーヴィットにとってとりわけ後者は許しがたいものでした。なぜなら彼らは、こういった考えが結果として、合理的な科学と出処のよくわからない迷信の区別をあいまいにする危険性があると考えたからです。
言い換えるなら、科学の対象(科学的な法則や物質など)は単純に実在し、科学的言説はまさにそれらを記述しているためにほかの知識体系(宗教や疑似科学など)より価値があるというのが、グロスとレーヴィット、ひいては大方の科学者の見解でした。
その後、こういった批判に対し、科学論者側から反論が試みられます。たとえば、当時カルチュラル・スタディーズ研究の牙城となっていた雑誌『ソーシャル・テクスト』も、科学論者による議論を擁護するために、その名も「サイエンス・ウォーズ」と題する特集を組みます。
この特集に掲載されたひとつの論文をめぐって、科学者と科学論者の論争はさらに混迷を深めていくことになります。
1-3:ソーカル事件
学術雑誌『ソーシャル・テクスト』は、ニューヨーク大学のアンドリュー・ロスなどによって編集されていた有名な雑誌です。
繰り返しになりますが、本誌が企画した企画「サイエンス・ウォーズ」は、『高次の迷信』への反論として、科学論者たちの主張の擁護を目指したものです。
結果として、1996年に刊行された『ソーシャル・テクスト』には科学論を擁護する多くの論文が掲載されましたが、そのなかでもとくに注目すべきは、ロスと同じくニューヨーク大学に属する物理学者アラン・ソーカルにより執筆された「境界を侵犯すること:量子重力論の変換的解釈学に向けて」という論文です。
この論文は科学者によって執筆されたにもかかわらず科学論の基本的な考え方を踏襲していたため、編集者であるロスらは、いわば「敵」である科学者側から思わぬ援軍を得たとしてソーカルの動きを歓迎しました。
しかしソーカルの真のねらいは、科学論の推進などではありませんでした。『ソーシャル・テクスト』誌上に論文が掲載されたわずか三週間後、ソーカルはまた別の雑誌で、以下の内容を暴露します。
- 「境界を侵犯すること」は科学論の言説を適当につぎはぎして作成したいわばパロディであり、その議論に真面目な主張など存在しないこと
- そこではまた、科学教育の受けたものなら誰で知っている基礎的な科学理論を意図的に誤用していること
すなわち、ソーカルのねらいは、『ソーシャル・テクスト』の編集部にあえて偽論文を送り込み、科学を居丈高に糾弾する科学論者(この場合、ロスら雑誌の編集部)が、いかに自然科学を理解していないかを明らかにすることにありました。
のちに「ソーカル事件」と名付けられるこの挑発的行為は、『ニューヨーク・タイムズ』などの一流紙に大々的に取り上げられ、『高次の迷信』が発刊されたとき以上の反響と賛否両論を巻き起こします。
また、ソーカルの科学論批判もこの事件だけで終結したわけではありませんでした。論文掲載から一年後の1997年に、ソーカルはベルギーの理論物理学者ブリクモンとともに『「知」の欺瞞』という書籍を出版します。
(2025/07/12 16:25:15時点 Amazon調べ-詳細)
『「知」の欺瞞』の内容
- ラカン、クリステヴァ、イリガライ、ラトゥール、ボードリヤール、ドゥルーズとガタリ、ヴィリリオなど著名な哲学者の著作で、科学的な概念や理論がいかに「濫用」されているかを指摘するもの
- 同時に、科学の「客観性」や「実在」を否定する科学論がいかにナンセンスであるかを告発するためのもの
こうしたソーカルの一連の行為をきっかけに、科学者と科学論者の相互不信と交流の断絶は頂点をきわめ、両者の論争はまさに「戦争」の様相を呈していきます。以上がサイエンス・ウォーズの概要です。
科学のあり方をめぐって、1990年代のアメリカでは、科学者と科学論者のあいだで上記のような激しい論争が繰り広げられました。
以下では、科学者と科学論者のあいだで争われた論点を再度整理し、サイエンス・ウォーズという現象をさらに具体的に分析していきましょう。
- サイエンス・ウォーズとは、1990年代のアメリカを主な舞台に、自然科学のあり方をめぐって科学者と科学論者(自然科学を論じる人文・社会学系の研究者)のあいだで交わされた激しい論争のことである
- 科学があつかう対象のアプリオリで中立的な実在を認めず、科学的な概念や理論体系といえども、社会的・文化的条件に拘束されていると考える点が議論の中心となった
2章:サイエンス・ウォーズで争われた主な論点
サイエンス・ウォーズではさまざまな観点から議論が交わされましたが、突き詰めるならその核心は、科学者が提出する科学的な言説は社会的・文化的に構築されたフィクションであるか、それとも、時代や地域を限定せずに通用する普遍的な真理であるか、という点に収斂します。
もちろん、ソーカルの偽論文が学術研究のルールや倫理に反しているのではないかということ、人文・社会学系の学者が基本的な自然科学の公理さえ理解せずに論を展開しているのではないかということも、激しい議論が交わされた重要な論点です。
しかし、科学的言説の本質を問う先述の論点をめぐる見解の違いが、サイエンス・ウォーズが生じるに至った根本的な原因であったと言えます。以下では、このことをさらに詳しく見ていきましょう。
まず確認しなければならないのは、近代科学とりわけ20世紀以降の科学が、金銭や設備の面で国家や産業界の支援のもとで成立しているということです。
- この点において、近代の科学研究が社会的・文化的条件に制約を受けているという主張には異論の余地はない
- このことは科学論者のみならず、ほかならぬソーカルをふくめた多くの科学者が認めている
ただし、科学者と科学論者とではこうした事実の受け止め方が異なります。
事態を単純化して説明するなら、科学者側が科学の概念体系それ自体は社会的な影響を受けず存在する純粋な「事実」であると考えたのに対し、科学論者側は知識の内容にまで社会的・文化的な影響が及んでいると考えました。
それでは結局のところ、どちらの言い分が正しいのでしょうか?おそらくこうした問いの立て方は適切ではありません。なぜなら、両者の主張にはそれぞれ納得できる側面があるからです。たとえば、次の点を考えてみてください。
- 自然科学のなかでもとりわけ生物学に関しては、知識自体に政治的かたよりやジェンダーバイアスが比較的強くあらわれていると言え、科学論者の主張が大きな説得力を持っている
- それに対して、科学論者がときとしておこなう強引なこじつけや極端な政治還元主義を見ると、科学の客観性やそのナイーヴな実在を主張する科学者の心情についても充分に理解できるものがある
今後、サイエンス・ウォーズという不幸なすれ違いを繰り返さないためにも、科学者と科学論者が手を取り合い、自然科学のなかでもそれぞれの分野や専門領域の特徴を充分に考慮した柔軟な姿勢で科学のあり方を議論することが求められていると言えます。
3章:サイエンス・ウォーズに関するおすすめの本
サイエンス・ウォーズの理解を深めることができましたか?
紹介した内容はあくまでも一部ですので、以下の書物を参考にさらに学びを深めていってください。
オススメ度★★★ 金森修『サイエンス・ウォーズ』(東京大学出版会)
タイトルが示す通り、サイエンス・ウォーズを論じた著作です。その背景から経緯までかなり詳しく解説されているため、サイエンス・ウォーズの全容を知りたい方にはおすすめです。
オススメ度★★ 野家啓一『科学の解釈学』(講談社)収録
本書には、「科学のナラトロジー(物語り論)」を提唱する著者が独自の視点からサイエンス・ウォーを読み解いた論文、「現代科学論とサイエンス・ウォーズ」が収録されています。とりわけソーカルとブルクモンの『「知」の欺瞞』について重点的な解説が試みられています。
(2025/07/12 16:25:16時点 Amazon調べ-詳細)
オススメ度★★★ アラン・ソーカル、ジャン・ブリクモン『「知」の欺瞞——ポストモダン思想における科学の乱用』(岩波書店)
ソーカルとブリクモンによる『「知」の欺瞞』の日本語訳です。サイエンス・ウォーズを知るにはやはり本書を読まないわけにはいきません。著名な哲学者による科学の「濫用」を非常に分かりやすく指摘しています。また巻末には、ソーカルが『ソーシャル・テクスト』に投稿したパロディ論文「境界を侵犯すること」も付載されています。
(2025/07/12 16:25:15時点 Amazon調べ-詳細)
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
Amazonオーディブル無料体験の活用法・おすすめ書籍一覧はこちら
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- サイエンス・ウォーズとは、1990年代のアメリカを主な舞台に、自然科学のあり方をめぐって科学者と科学論者(自然科学を論じる人文・社会学系の研究者)のあいだで交わされた激しい論争のことである
- 科学があつかう対象のアプリオリで中立的な実在を認めず、科学的な概念や理論体系といえども、社会的・文化的条件に拘束されていると考える点が議論の中心となった
- 科学者と科学論者が手を取り合い、自然科学のなかでもそれぞれの分野や専門領域の特徴を充分に考慮した柔軟な姿勢で科学のあり方を議論することが求められている
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら