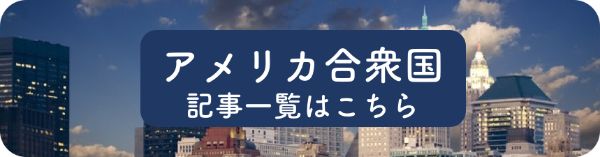サルトルの実存主義とは、人間の生きる意味を自己の中ではなく、生きる世界との関係の中で決定するべきであると考える哲学思想です。
サルトルの実存主義は構造主義による批判に晒されましたが、その重要性は衰えていません。むしろ、今日こそ学ぶべき内容が多くあります。
そこで、この記事では、
- サルトルの伝記的情報
- サルトルの実存主義の特徴
- サルトルの実存主義への批判
好きな箇所だけでも構いませんので、ぜひ読んでみてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:サルトルの実存主義とは
1章ではサルトルの実存主義を概説します。2章では具体的な内容から深掘りしますので、用途に合わせて読み進めてください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:サルトルの伝記的情報
ジャン・ポール・サルトルは、1905年6月21日にパリで生まれました。サルトルが生まれてまもなく、1907年に海軍将校であった父が亡くなります。そしてその後、母が1916年に再婚しました。
つまり、サルトルは実の父を知らず、母の再婚を経験するという少々複雑な幼少期を生きることになりました。
サルトルは、1915年にアンリ四世高等中学校に入学します。この時の級友には、後のコミュニスト作家であるポール=ニザンがおり、精神的に大きな影響を受けています。
その後、1924年、パリのエコール・ノルマルに入学します。同級生には、以下のような人々がいました。
エコール・ノルマルでの同級生
- 先ほどのポール=ニザン、レイモン=アロン(後のパリ大学社会学教授)
- モーリス=メルロ=ポンティ(リヨン大学・ソルボンヌ大学・コレージュ-ド-フランスを歴任した教授であり、サルトルとならぶ現代フランスを代表する現象学者)
- ジョルジュ=ポリツェル(マルクス主義哲学者、後にナチスの占領下でゲシュタポに捕らえられ、1942年に銃殺される)
- シモーヌ=ド=ボーヴォワール(哲学者であり、サルトル夫人)など
このエコール・ノルマルでの優れた学友との出会いが後のサルトルの思想に大きな影響を及ぼしました。特に、後に契約結婚という形で夫婦となるボーヴォワールの存在は、サルトルの思想を語る上で外すことができないでしょう。
サルトルの執筆活動に関しては、次のようにまとめることが可能です。
- サルトルは1933年にベルリン留学を行い、フッサールやハイデガーの哲学を学ぶ
- 特に、サルトルは、この留学でフッサール現象学について深く学び、その影響を受けながら1936年に『想像力』、1937年に『自我の超越』を発表した
- さらに、1938年に小説『嘔吐』を発表し、実存思想の原型となる思索を展開している
- また1943年に主著である大著『存在と無』を発刊し、サルトルの哲学的なマニフェストが表明される
- その後、サルトルの執筆活動は、1961年の『弁証法的理性批判』を除いて、ほとんどがマルクス主義的な政治思想を中心に行われることになった
そして、1952年のカミュとの論争や、1964年のノーベル文学賞辞退を経て、1980年4月15日に75年の生涯を終えました。
以上がサルトルの簡単な伝記的な情報です。それでは、彼の哲学をいかなる思想なのでしょうか。次に、この点を説明しましょう。
1-2:サルトルの実存主義の特徴
ここでは、サルトルの思想の特徴を大まかに説明します。伝記でも説明したように、サルトルの思想は、(特に初期に関して)フッサール現象学から多分に影響を受けています。
それゆえ、ここでは、フッサール現象学との違いを見ていくことでサルトル哲学の輪郭を明らかにしていきましょう。
1-2-1:フッサール現象学の特徴
フッサール現象学の特徴は、私たちにとって存在しているものが意識の働きによって成立していると考えることです。
その時、意識は「何ものかについての意識である」という構造を持つとされます。これをフッサールは「志向性(Intentionalität)」という言葉で呼んでいます。
すなわち、フッサールは次の点を主張しました。
- 意識とは決してそれ自身で存在するのではなく、何らかの対象を求めて志向し、何ものかに向かい合うということなしには存在できない
- 言い換えると、物が意識の志向的対象であるならば、事物は意識が志向性を向ける限りにおいてしか現れないことになる
それゆえ、意識のあり方が変化するならば、事物の現れ方も変化することになります。この事態をコップを例にして考えてみましょう。
コップの例
- 日常的に私たちは、コップを「何かを飲むもの」として意識している
- このとき、事物の現れ(あるいは意味)は暗黙のうちに固定化されている
しかし、一度コップを「何かを飲むためのもの」という前提から離れて捉えたとき、いままで「コップ」と呼ばれていたものは、どのように現れてくるでしょうか?
フッサールはそのとき捉えられるものが「本質」であると考え、サルトルはこのとき私たちが捉えているのは、コップの「存在」そのものだと考えます。
この点については、両者に特筆するほどの差異はありません。
フッサールの現象学に関しては、こちらでより詳しく解説してます。→【フッサールの現象学とは】伝記的情報・特徴・概念をわかりやすく解説
1-2-2:サルトルとの差異
しかし、ここからがフッサールとサルトルの差異が際立ってきます。両者の違いは次のようにまとめることができます。
- フッサール・・・志向的対象は意識によって把握されたものとなる限り、意識の内容となり、意識の内部に存在するもの、意識に内在するものとなる
- サルトル・・・フッサールとは異なり、対象がたとえ意識によって志向されたものであろうとも、それ自体はあくまでも意識の外にあるものだと考える
サルトルがこのように考えるのは、フッサールのように対象が意識に内在するものであるならば、対象は意識によって意識化されることになるためです。もしそうであるならば、意識によって変化させられた対象は意識の奴隷であり、対象それ自体ではないことになってしまいます。
それゆえ、サルトルは、フッサールが述べるような、一般にまず本質(対象そのものの意味)があって、これに合わせて意識のあり方を変えるという本質主義を批判しているのです。
以上のことから、サルトル哲学の基本姿勢が明らかになります。すなわち、サルトルは意識、あるいは人間が自らに先立って決定されているものにただ従うのではなく、自らの意味を自分の自身で規定していくことを目指したものだと言えます。
そして、サルトルは、この思想を「実存主義」と呼びました。
- サルトルの実存主義とは、人間の生きる意味を自己の中ではなく、生きる世界との関係の中で決定するべきであると考える哲学思想である
- サルトルは意識、あるいは人間が自らに先立って決定されているものにただ従うのではなく、自らの意味を自分の自身で規定していくことを目指した
2章:サルトルの実存主義の内容
さて、2章では1章で説明した実存思想の内実をさらに詳しく見ていきましょう。
2-1:「実存は本質に先立つ」
サルトルは、実存主義の中心的なテーゼを「実存は本質に先立つ」という言葉で表現しています。ここでの実存は「人間の現実的な存在」という意味です。
すなわち、「実存は本質に先立つ」とは、
私たち人間の現実的な存在は、私たちがいかなる存在者であるかという規定(あるいは意味)が行われて形成されるわけではなく、まず存在していること
を表現しています。
言い換えると、私たちは、自らがどのような人間存在なのかを規定する設計図(本質)に基づいて存在するのではなく、存在する中で自らがいかなる存在なのかを決めていく存在者という主張です。
2-2:ペーパーナイフの例 ―『実存主義はヒューマニズムである』―
「実存は本質に先立つ」という主張を具体的な例で考えてみましょう。ちなみに、この例は、サルトル自身が『実存主義はヒューマニズムである』という著作の中で出している有名な例です。
この例の中で、まずサルトルは人間存在ではなく、事物存在を表す「本質が実存に先立つ」という事態から説明を始めています2『実存主義はヒューマニズムである』、伊吹武彦訳、39-40頁。
例えば、書物とかペーパーナイフのような作られたある一つの物体を考えてみよう。この場合、この物体は、一つの概念を頭に描いた職人によって作られたものである。職人は、ペーパーナイフの概念に頼り、またこの概念の一部をなす既存の製造技術―結局は一定の製造法―に頼ったわけである。したがって、ペーパーナイフは、ある仕方で作られる物体であると同時に、一方では一定の用途を持っている。この物体が何に役立つかも知らずにペーパーナイフを作る人を考えることはできないのである。ゆえに、ペーパーナイフに関しては、本質―すなわち、ペーパーナイフを製造し、ペーパーナイフを定義しうるための製法や性質の全体―は、実存に先立つと言える
この引用から分かるように、ペーパーナイフという事物は、「手紙の封を開ける」ためのものとして作られています。
すなわち、私たちが日頃使用している事物は、その事物が本来的に果たすべき目的を達成するためのものとして職人によって作られているのです。それゆえ、ペーパーナイフは、その存在(=実存)よりも「~のために」という本質が先に立っているといえます。
これに対して、人間存在の「実存は本質に先立つ」とは、次のような事態です3同上、41-42頁。
私の代表する無神論的実存主義は、一層論旨が一貫している。例え神が存在しなくても、実存が本質に先立つところの存在、何らかの概念によって定義されうる以前に実存している存在が少なくも一つある。その存在はすなわち人間、ハイデガーのいう人間的現実である、と無神論的実存主義は宣言するのである。実存が本質に先立つとは、この場合何を意味するのか。それは、人間はまず先に実存し、世界内で出会われ、世界内に不意に姿を現し、その後で定義されるものだということを意味するのである。実存主義の考える人間が定義不可能であるのは、人間は最初は何ものでもないからである。人間は後になって初めて人間になるのであり、人間は自ら作ったところのものになるのである。このように、人間の本性は存在しない。その本性を考える神が存在しないからである
ここで述べられている「無神論的実存主義」はサルトルが自らの実存主義を呼ぶ際の呼び方です。
それが「無神論的」とされるのは、引用からも分かるように、人間存在にはその存在を規定する「神」という創造主(事物の場合は職人)がいないために、「無神論的」と呼ばれます。
それゆえ、人間はその存在の意味を事物のようにあらかじめ決められているわけではなく、存在している中で自らの存在の意味を作り出していくのです。
ちなみに、哲学史などでは、キルケゴールやヤスパースなどが「有神論的実存主義」とくくられることがあります。それの思想に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
2-2-1:アンガジュマン
それでは、私たち人間は、実存する中でどのように自らの本質を決定していくのでしょうか?
サルトルによれば、それは私たちが生きている世界の「状況」の中で、どのような決断をしたのかによって決定されるといいます。たとえば、「根はいい人だが、現実的には悪いことばかりをしている人」は、サルトルの考えでは「悪者」として評価されることになります。
言い換えれば、
私たちは自らが生きている世界に「投げ込まれて」おり、そのような状況の中でいかにしてこの世界(あるいは社会)に関わっていくかによって、私たち人間の本質は決定される
といえます。
この社会への関わりをサルトルは「アンガジュマン(engagement)」という言葉で表現しました。このアンガジュマンは、あえて日本語へ訳すと「自己拘束」「社会参加」「責任敢取」となります。
このようなアンガジュマンを通じて、与えられた状況の中に身を投じ、主観的な判断に基づいて自らが下した判断の責任を引き受けつつ、そのような責任の中に生きることで自らの生きる意味を見出すのがサルトルが考える実存主義の根幹思想と言えるでしょう。
- 人間とは、自らがどのような人間存在なのかを規定する設計図(本質)に基づいて存在するのではなく、存在する中で自らがいかなる存在なのかを決めていく存在者である
- 私たちが生きている世界の「状況」の中で、どのような決断をしたのかによって「本質」は決定される
3章:サルトルの実存主義の影響と批判
3章では、サルトルの実存主義の影響と、それに対する批判を説明します。この際に、取り上げるのは「カミュとの間で行われた論争」と「レヴィ=ストロースとの論争」です。
3-1:サルトル vs カミュ
2章では、サルトルの実存主義の根幹部分を説明してきました。それによれば、私たち一人一人の主体が自らの置かれた状況に関わる決断をして、その決断の責任を引き受ける中で生きる意味が決まっていくというのが、サルトルの実存主義でした。
この状況への関わり方という点でサルトルが厳しく糾弾したのが、旧友であったアルベール・カミュ(Albert Camus)でした。カミュは、『異邦人』や『ペスト』という著作で日本においても著名な作家で、彼の小説は「不条理」をテーマとしているものが多いです。
さて、サルトル=カミュ論争を見ていく中で、重要なのが「歴史」というものの捉え方です。
サルトル思想の歴史
- 私たちが投げ込まれている世界は、ある歴史を持っている
- それゆえ、私たちが投げ込まれているのは、「ある歴史的状況」であるとも言える
- 特に、彼らが活躍した1940−1960年代は、第二次世界大戦や植民地解放などの歴史的な変動が多かったことも、この思想に影響していると言えるかもしれない
ところで、そのような歴史にある「流れ」の法則性が存在し、それを正しく理解することができるとしたら、私たちは歴史的状況の中で正しく生きることができるのではないでしょうか?
サルトルもそこに含まれるマルクス主義者によれば「歴史の法廷」は「歴史を貫く鉄の法則性」に支配されています。それゆえ、歴史の「鉄の法則性」を知っているものは、ある歴史的状況での生き方を誤ることがない、ということになります。
- サルトルが批判したカミュは、第二次世界大戦中のパリでレジスタンス活動を行い伝説的闘士として讃えられていた
- しかし、サルトルは、カミュがある時期の歴史的状況での正しい生き方を変化させず、その立場に固執したために戦後の第三世界の民族解放闘争(アルジェリア戦争=フランスの植民地支配に対する独立戦争)にコミットしなかったして批判している
- すなわち、歴史的状況が変化し、そこには「法則性」が存在していることをカミュは理解していないとサルトルは、処断している
この論争をきっかけにサルトルとカミュは絶縁状態になってしまいます。
3-2:サルトル vs レヴィ=ストロース
このように、サルトルの実存主義はカミュとの論争を経て、一度は排除した「神の視点」を「歴史」と言い換えて再登場させることになりました。
つまり、サルトルは「実存は本質に先立つ」と言いつつも、その「実存」が「歴史」に支配されていることを主張していることになります。
レヴィ=ストロースが批判したのは、まさにこの点でした。
- 主体が与えられた状況の中で決断することで自己の意味を形成するという点について、サルトルとレヴィ=ストロースの差異はない
- しかし、状況の中で主体は常に「政治的に正しい」選択を行うべきであり、その「政治的な正しさ」はマルクス主義的歴史認識によって保証されるという点については、両者の主張は食い違うことになる
レヴィ=ストロースもまた、サルトルの旧友であり、構造主義という新しい哲学理論を生み出した人類学者です。
レヴィ=ストロースが著した『野生の思考』は、いわゆる「未開人」と言われる人々が世界をどのようにして経験し、どのように秩序付けているかを記述したものでした。
構造主義や『野生の思考』に関して本記事では記述していませんので、以下の記事を参照ください。
レヴィ=ストロースが「未開人」のフィールドワークなどを通じて明らかにしたものは、たとえ西洋文明において「未開人」と呼ばれる人々であったとしても決して人間としての「尊厳」や「理性」が欠如しているとは考えられない、ということでした。
すなわち、「未開人」を「未開」と呼ぶことは、自分たち(=西洋文明の人々)を文明人であると思い込み、他人(=「未開人」とされる人々)の世界を「主観的で歪んだ世界」と考える極めて傲慢な見方なのです。
※西洋の一元的なモノの見方を批判するのが文化人類学という学問の特徴の一つです。詳しくはこちらの記事→【文化人類学とは】学問の特徴から文化の定義までわかりやすく解説
さらに、レヴィ=ストロースは、サルトルが歴史という「物差し」を使って「歴史的に正しい決断をする人間」と「歴史的に誤りを犯す人間」を峻別するやり方は、彼らが「未開人」と呼ぶ人々が自らの「物差し」を使って物事を区別しているやり方と本質的には変わらないと述べます。
そのうえで、レヴィ=ストロースは、やや皮肉的にサルトルを次のように批判します4『野生の思考』、大橋保夫訳、「第9章 歴史と弁証法」。
サルトルの哲学のうちには、野生の思考のこれらのあらゆる特徴が見いだされる。それゆえに、サルトルには野生の思考を査定する資格はないと私たちには思われるのである。逆に、民族学者にとって、サルトルの哲学は第一級の民族史的資料である。私たちの時代の神話がどのようなものかを知りたければ、これを研究することが不可欠であろう。
すなわち、サルトルの哲学それ自体がある狭い歴史的状況の中での一観点に過ぎず、それがあらゆる人間の生き方を決める指針とはなりえないのです。
以上のような批判によってサルトルの実存主義は、急激に影響力を失い、構造主義の時代へと変化していくことになります。
- サルトルによれば、歴史の「鉄の法則性」を知っているものは、ある歴史的状況での生き方を誤ることがない
- サルトルは「実存は本質に先立つ」と言いつつも、その「実存」が「歴史」に支配されていることを主張している
4章:サルトルの実存主義を学ぶための本
サルトルの実存主義に関する理解を深めることはできましたか?
最後に、サルトルの実存主義を学んでみたいという方に向けて解説本から学術本まで紹介していきます。
村上嘉隆『サルトル 思想と人34』(清水書院)
手に入れやすく、サルトルの生涯と思想を極めて密接に関連付けて解説している入門書です。実存主義から政治思想までの広い内容をカバーしています。
J-P.サルトル『実存主義とは何か』(人文書院)
タイトルにもあるように、実存主義についてサルトル自身が語っている論文集です。書き方も平易ですので初学者の方でも手に取りやすいと思います。ただし、内容までも平易とは限りません。ぜひじっくりと取り組んでいただきたい一冊です。
内田樹『寝ながら学べる構造主義』(文藝春秋)
本記事でのサルトルとカミュ、レヴィ=ストロースの論争で参考にした書籍です。テーマは、サルトルではなく構造主義がメインですが、(サルトルも含めた)サルトル以降のフランス哲学の流れを理解したい方はぜひ手にとってみてください。
書物を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは1ヶ月無料で利用することができますので、非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、気になる方はお試しください。
まとめ
- サルトルの実存主義とは、人間の生きる意味を自己の中ではなく、生きる世界との関係の中で決定するべきであると考える哲学思想である
- 人間とは、自らがどのような人間存在なのかを規定する設計図(本質)に基づいて存在するのではなく、存在する中で自らがいかなる存在なのかを決めていく存在者である
- サルトルは「実存は本質に先立つ」と言いつつも、その「実存」が「歴史」に支配されていることを主張している
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら