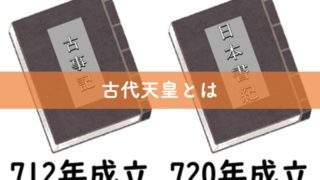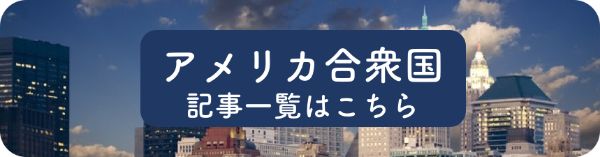間テクスト性(intertextuality)とは、いかなるテクスト(意味や情報を伝達する文字の羅列)も、それのみが独立して存在しているのではなく、先行する多くのテクストとの関連のなかではじめて存在する、ということを指す概念です。
この概念の出現によって、従来、自己完結した意味内容(作者の意図など)を伝達する自閉的なツールとして捉えられていたテクストを、社会、文化、歴史といったテクストの外部と関連させて論じることが可能となりました。
間テクスト性は、現代の文芸批評において、もっとも基本的な指針を形成しています。
これはすなわち、広い意味で文芸作品(文学、絵画、映画、建築、音楽、漫画、アニメなど)、ひいては、あらゆるジャンルの言述の機能や成り立ちを深く理解するには、間テクスト性という考え方が不可欠である、ということです。
そこで、この記事では、
- 間テクスト性の概要
- 間テクスト性をめぐる代表的議論
について解説します。
具体例を交えて丁寧に解説するので、興味のある方はぜひご覧ください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:間テクスト性とは
1章では、間テクスト性の概要について解説します。以下ではひとまず、(「間テクスト性」という用語の発明者である)クリステヴァの議論に焦点を絞ります。間テクスト性には多くの見解が存在しますが、この概念の要点を知るうえで、彼女の議論はとくに重要です。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:クリステヴァの議論
クリステヴァはブルガリア出身の哲学者、記号学者、文学理論家で、留学先のパリでは、ゴルトマンやロラン・バルトに師事しました。クリステヴァは晦渋なフェミニズム研究で有名ですが、本記事では、彼女が1960年代後半に従事した記号論的、文学理論的研究に注目します。
具体的には、以下の著作が重要です。
- 『セメイオチケ——記号分析学のための探究』[1969年刊行]
(2024/04/26 16:28:36時点 Amazon調べ-詳細)
- 『テクストとしての小説』[1970年刊行]
(2024/04/26 16:28:37時点 Amazon調べ-詳細)
前者は、フランスの古い小説である『ジャン・ド・サントレ』を分析したもの(クリステヴァの博士論文を書籍化したもの)、後者は、1969年までに執筆された論文を整理したものです。
これらの著作によってクリステヴァは、現代文芸批評の基礎となる間テクスト性の理論を分かりやすく提示しました。
1-1-1:議論の背景
まず、クリステヴァが間テクスト性を論じるに至った背景を確認します。1960年代当時、フランス思想界を席巻していたのは、ソシュールの記号論を起源を持つ構造主義でした。
構造主義とは、あらゆる現象の背後で機能する構造(すなわち要素間の関係性)を抽出し、そこから個別の出来事を思考しようとする方法論を指します。レヴィ=ストロースの神話研究、アルチュセールのマルクス読解、バルトの記号論に、その具体的な表出を見て取ることができます。
これに対してクリステヴァは、テクストという対象を論じるにあたって、構造主義の有用性を認めつつも、その限界を指摘します。具体的には、次のようなものです。
- 批判の矛先はとりわけ、構造主義の議論が、外部に閉ざされ、自己完結した構造をあつかうために、構造の外部にあるもの、および、それが構造に与える影響について言及できないことへと向けられた
- それゆえ、構造主義の成果を前提にしながらも、それを乗り越えるためのあたらしい理論体系(彼女はこれを「記号分析学」と名付けます)の構築を試みた
そして「間テクスト性」とは、こうした背景のもと、まったくあたらしいテクスト理論を構築するために、彼女が考案した概念装置のひとつでした。
ちなみに、1960年代後半から1970年代後半にかけてフランスでは、クリステヴァに限らず、構造主義の乗り越えを目指す思想運動が活発でした。こうした運動はポスト構造主義と呼ばれ、既存の政治体制へ異議を申し立てた学生運動(五月革命)と呼応することで、世界中に広がっていきました。
※構造主義からポスト構造主義までの議論の流れは、『フランス現代思想史』(中公新書)がわかりやすいです。
(2022/03/12 02:11:39時点 Amazon調べ-詳細)
1-1-2:議論の内容
それでは、クリステヴァの議論を確認していきましょう。すでに述べたように、クリステヴァはテクストを、それ単体で完結した対象としては考えません。彼女は、テクストを絶えずその外部と交信する空間として理解しようと試みます。
そして、こういった野心的試みのなかで、ロシアの文芸批評家ミハイル・バフチンの文学理論を継承しつつ、クリステヴァがあたらしく考案した概念が「間テクスト性」でした。
クリステヴァは間テクスト性の理論をあらゆる側面から語っていますが、以下の発言にはその要点が凝縮されています2クリステヴァ『記号の解体学——セメイオチケ1』(原田邦夫訳、せりか書房)、61頁。
いかなるテクストも、さまざまな引用のモザイクとして形成されており、すべてのテクストは他のテクストの吸収であり、変形にほかならない。
ここでクリステヴァは、あるひとつのテクストが、けっしてそれのみで孤立しているのではないこと、そして、先行する多くのテクスト(すなわち「テクストの外部」)と、「引用」という技法により深く関係していることを強調しています。
もちろん、ここで言われる「引用」は、学術的なルールにしたがって他人のテクストを転載する行為に限定されるべきではありません。クリステヴァが意図しているのは、模倣、オマージュ、パロディ、借用、剽窃など、ありとあらゆるレベルでなされるすべての「引用」です。
ひとつのテクストは、上記の仕方で、数えきれないほど多くの先行するテクストと関連しながら、すなわち、先行するテクスト(また同時に、先行するテクストに先行するテクスト)が織りなす広大なネットワークのなかで存在している、ということです。
- クリステヴァはまた、先行するテクストとのこういった関わりのことを、バフチンの用語を引き継ぎ、テクストの外部(先行するテクスト)との「対話」と呼んでいます。
- 彼女が見るところ、テクストとは、先行するテクストを、ときにはその意味を変形させながら受け継ぐことで成立しているわけです。
そして、この概念の導入によって、それまでとは異なる、まったくあたらしいテクスト理解が出現したと言えます。
なぜなら、あらゆるジャンルの言述を、厚く積み重なった先行テクストとの関わりのなかで、すなわち、その外部を視野に入れて思考することが可能となったからです。
ただ、上記の説明だけでは分かりにくいので、以下ではさらに、クリステヴァが具体的なテクストに言及しながら議論を展開している箇所を確認してみましょう。
1-1-3:ロートレアモン『ポエジー』の分析
ここで注意する必要があるのは、哲学書であれ、漫画やアニメであれ、あらゆるテクストが間テクスト的に成立している、ということです。ただ、その現出の度合いには、言述のジャンルごとに濃淡があります。
たとえば文学テクストにおいては、比較的容易に、ほかのテクストからの「引用」と思われる箇所を指摘し、その機能を分析することができます。クリステヴァもこれと同様の認識をもっていたため、彼女が分析の対象としたのは、ほとんどが文学テクストです。
ここでは、彼女がきわめて間テクスト的に構成されていると判断し、集中的に分析したロートレアモンのテクスト、そのなかでも『ポエジー』というテクストを例にとり、クリステヴァの議論を振り返ってみましょう。
ロートレアモンの『ポエジー』は、次の意味でとても奇妙な作品です。
- 多くのひとは『ポエジー(詩)』というタイトルから、ロートレアモン独自の感性に基づくオリジナリティあふれた描写を期待する
- しかし、この作品の大部分は驚くことに、すでに存在するテクスト、さらに、フランス文化に馴染んだひとなら当然知っているはずのテクスト(パスカル、ラ・ロシュフーコーなどの有名なテクスト)の変形として成り立っている
たとえば、次の例をみてください。
ロートレアモンは、パスカルの
「ひとが話題にしてくれさえすれば、われわれは喜んで命までをも失う」
というある種の警句を、
「ひとが絶対に話題にしないというのなら、われわれは喜んで命を失う」
と文の一部を変形(前半の節を否定形に変形)して、使用しています。
ロートレアモンの後者の文章を読んだとき、フランス文化をよく知るひとならば、パスカルによる前者の文章を否応なく連想します。
そしてここでは、パスカルが述べる真理(と広く受け入れられているもの)が、文章をほんの少し変えただけで消滅し、まったく異なる意味を獲得していることを見て取ります。
すなわち、ロートレアモンのテクスト空間においては、先行するテクストとの(この場合は、否定的な)「対話」が実施され、この「対話」のなかで意味があらたに生成している様子を、分かりやすく観察することができます。
クリステヴァはこうして、あらゆる言述が先行するテクストとのネットワークのなかで存在していることを、具体的な作品分析をとおして提示しているのです。そして、引用がどのように折り重なっているかを解明することが、クリステヴァの記号分析学の核心にほかなりません。
1-2:間テクスト性の具体例
すでに見たように、クリステヴァは主に、フランス語圏の文学作品を分析対象としています。しかしフランス文学以外にも、あらゆるテクストについて間テクスト性を議論することができます。いかなるテクストも、その本質は「引用のモザイク」にほかならないからです。
ここでは理解を深めるため、いくつかの事例を、間テクスト性という観点から考えてみましょう。
1-2-1:本歌取り
本歌取りとは、
和歌の表現技法のひとつで、有名な和歌の一節を自作に取り入れて作歌する手法
です。
具体例は挙げませんが、この技法が間テクスト性と深く関わることは明らかです。
すなわち古人たちは、一首のあたらしい和歌が、すでに存在する和歌をうちに取り込むことではじめて生成することを明確に認識し、それをひとつの技法にまで高めたと言えます。
1-2-2:『1Q84』
『1Q84』は、2009 ⁄ 2010年に発刊された村上春樹の小説です。タイトルから分かるように、この作品は、ジョージ・オーウェルの有名なディストピア小説『1984年』を土台に執筆されています。
この小説を読むひとは否応なくオーウェルの『1984年』を連想し、両者を比較しながら作品を理解します。つまり、『1Q84』という小説は、先行するテクストとの絶えざる対話を抜きにして語ることができないテクストなのです。
さらに、オーウェルの『1984年』はふつう、トマス・モアの『ユートピア』など、ディストピア小説の系譜に連なる作品として理解されます。
(2024/04/26 16:28:38時点 Amazon調べ-詳細)
すなわち、『1Q84』がオーウェルと深い関係をもっていることは、
このテクストが実のところ、オーウェルの『1984年』のみならず、『ユートピア』に代表されるあらゆるディストピア小説との対話によって成立している
ということです。
このように、自己完結したテクストなど存在せず、四方八方に広がる先行テクストの網の目のなかではじめて、ひとつのテクストは成り立っているのです。
- 間テクスト性とは、いかなるテクストも、それのみが独立して存在しているのではなく、先行する多くのテクストとの関連のなかではじめて存在する、ということを指す概念である
- 間テクスト性によって、あらゆるジャンルの言述を、厚く積み重なった先行テクストとの関わりのなかで、すなわち、その外部を視野に入れて思考することが可能となった
2章:間テクスト性をめぐる代表的議論
ここまではクリステヴァの議論を参考に、間テクスト性の概要を確認してきました。しかし、クリステヴァのみが間テクスト性の理論化に取り組んだのではなく、多くの記号論者が、それぞれの観点から議論を展開しています。
ここでは、理解をさらに深めるため、間テクスト性をめぐる代表的議論をいくつか確認してみましょう。
2-1:「作者の死」
繰り返しになりますが、間テクスト性という概念によって、あらゆる言述は「引用のモザイク」として理解されるようになりました。言い換えるなら、先行するテクストとの対話(これをコントールすることは作者といえども困難です)をとおして作者の意図を超越し、あたらしい意味内容を生成させる自律的空間としてテクストは捉えられています。
こうした理解は必然的に、作品が持つとされる「オリジナリティ」、あるいは、作品を生み出す天才的な「作者」、これらの概念の地位の低下をもたらします。
ロラン・バルト(彼はクリステヴァの師ですが、弟子である彼女の影響を受けて自身のテクスト論を発展させました)は、こうした状況を「作者の死」という概念を使って説明します。
バルトは、その名も『作者の死』という小論のなかで、以下のように述べています3ロラン・バルト『物語の構造分析』(花輪光訳、みすず書房)、85-86頁。
われわれは今や知っているが、テクストとは、一列に並んだ語から成り立ち、唯一のいわば神学的な意味(つまり、「作者=神」の〈メッセージ〉ということになろう)を出現させるものではない。テクストとは多次元の空間であって、そこではさまざまなエクリチュールが結びつき、異議を唱えあい、そのどれもが起源となることはない。テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物である。
バルトは、クリステヴァと共通の問題意識を持ちながらも、とくに「作者」という観点から、テクスト理論を洗練させた思想家です。
ここでバルトは、「引用の織物」であるテクストに、「〈メッセージ〉」を吹き込む「作者=神」の居場所がもはや存在しないことを、高らかに宣言しています。
- そもそも、多くの研究が示しているように、作品をつらぬく「オリジナリティ」や、作品を生み出す天才的な「作者」といったものは、いつの時代も受け入れられてきた普遍的概念ではない
- これらは、「個人」を基本的単位とする近代の社会構造、あるいは、それを法的に保護する「著作権」などの権利体系のなかではじめて機能する創造物にほかならない
歴史的に見れば、テクストとは「引用のモザイク」のことであり、そこに作者などいない、と考えていた時期のほうがはるかに長いのです。
たとえば、『桃太郎』や『一寸法師』といった伝統的なテクストに、特定の作者はいません。こういった種類のテクストは、絶えず語り直されることで、すなわち「引用」されることで、その意味を微妙に変化させながら受け継がれてきました。
この意味で、間テクスト性の考え方は、近代社会に対するアンチテーゼという側面をもっています。ちなみにフーコーも、『作者とは何か?』という小論で、バルトと類似した議論を展開しています。
2-2:読書行為
さて、作者がいないのだとすると、テクスト間の「対話」はどのように引き起こされるのでしょうか。この問いには、テクストが自律的に作用していると答えることもできますが、やはり読者という観点を視野に入れるべきです。
テクストが、先行するテクストと断続的な「対話」をはじめるには、先行するテクストと意識的、無意識的に触れ合ってきた読者の存在が欠かせません。
さまざまな書籍と触れ合ってきた読者がテクストを読むことによって、あるひとつのテクストが、先行するテクストと重層的に関係をもっていることが明らかになる、ということです。
すなわち、作者のメッセージを受け取る受動的な行為として捉えられてきた読書は、間テクスト性を基盤にしたテクスト論によって、テクスト間の対話をうながす能動的な行為として再定義されています。
読者の役割を積極的に評価するこういった文学理論は、1960年代後半に提唱され、受容美学と呼ばれています。
※テクスト論に関してはより詳しくは、こちらの記事を参照ください。→【テクスト論とはなにか】作品論との違いからバルトの議論まで解説
2-3:剽窃
広い意味での「引用」、すなわち、引用(通常の意味での)、模倣、オマージュ、パロディ、借用は、あらゆるジャンルの叙述を間テクスト的に考えるにあたって、つねに注目しなければなりません。これらは、テクストを成立させる基本操作であるからです。
これに対して、他人の文章を無断で書き写す行為、すなわち剽窃についてはどう考えられるでしょうか?
言うまでもなく、現代において剽窃は厳格に禁止されています。なぜなら、あらゆる文章はその作者の所有物であり、これを無断で使用することは、個人の権利をする行為であるとの考えが浸透しているからです。
しかしながら、クリステヴァやバルトにしたがって、あらゆるテクストを「引用のモザイク」と捉えるならば、剽窃を積極的に推奨しないまでも、この行為を再考する余地が生まれてきます。
この問題を考えるうえで、アルゼンチンの作家ボルヘスによる『「ドン・キホーテ」の著者、ピエール・メナール』は、きわめて示唆に富んだ小説です。
- 本作で記述されるピエール・メナールは、かの有名なセルバンテスの『ドン・キホーテ』を一字一句書き写し、現代において、オリジナルの作品としてその刊行を目論んだ男である
- この行為はもちろん剽窃であり、メナールの『ドン・キホーテ』を論じることは馬鹿馬鹿しいとも言える
しかし、本作の語り手は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』と比較して、メナールの『ドン・キホーテ』は「ほとんど無限に豊かである」4J. L. ボルヘス『伝記集』(鼓直訳、岩波書店)、65頁と評価します。
これはどういうことかというと、ポイントは、まったく同じ文章でありながらも、世に広まった時期が異なることにあります。
セルバンテスの『ドン・キホーテ』は、周知のように17世紀のテクストであるのに対し、メナールの『ドン・キホーテ』は、20世紀のテクストです。
これはすなわち、
メナールの『ドン・キホーテ』には、17世紀から20世紀のあいだ(つまり、セルバンテスの『ドン・キホーテ』が出版されてから、メナールの『ドン・キホーテ』が世に出るまでの期間)にあたらしく出現した膨大なテクストと、対話を繰り広げる可能性が開かれている
ということです。
その結果として、まったく同一の文章でありながらも、両者のあいだには、その意味内容に大きな違いが生まれてくる、というわけです。
- バルトは「引用の織物」であるテクストに、「〈メッセージ〉」を吹き込む「作者=神」の居場所がもはや存在しないことを宣言した
- 間テクスト性の立場に立てば、まったく同一の文章でありながらも、両者のあいだには、その意味内容に大きな違いが生まれてくる
3章:間テクスト性に関するおすすめの本
間テクスト性に関して理解を深めることはできましたか?
以下は深く学ぶためのおすすめ本です。ぜひ読んでみてください。
オススメ度★★★ 西川直子『クリステヴァ——ポリロゴス——(現代思想の冒険者たち30)』(講談社)
クリステヴァの晦渋な議論を、きわめて分かりやすく解説した入門書です。どちらかというと、彼女のフェミニズム論が解説の中心ですが、間テクスト性についても存分に論じられています。
オススメ度★★★ グレアム・アラン『文学・文化研究の新展開——間テクスト性——』(研究社)
間テクスト性という観点から、思想史を縦横無尽に読み解いた研究書です。間テクスト性というとクリステヴァに議論が集中しがちですが、本書では、ソシュール、バルト、ジュネットなども丁寧にテーマ化されています。ただ、若干翻訳が読みにくいのが難点です。
(2024/04/26 16:28:40時点 Amazon調べ-詳細)
オススメ度★★★ J. L. ボルヘス『伝記集』(岩波書店)
アルゼンチンの作家ボルヘスの小説集です。理論書ではないですが、「引用」がもたらす作用を主題にした、ある種の思考実験といえる小説がいくつも収められています。とりわけ、すでに言及した『「ドン・キホーテ」の著者、ピエール・メナール』は、「引用」を考えるうえで必須の書です。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 間テクスト性とは、いかなるテクストも、それのみが独立して存在しているのではなく、先行する多くのテクストとの関連のなかではじめて存在する、ということを指す概念である
- 間テクスト性によって、あらゆるジャンルの言述を、厚く積み重なった先行テクストとの関わりのなかで、すなわち、その外部を視野に入れて思考することが可能となった
- バルトは「引用の織物」であるテクストに、「〈メッセージ〉」を吹き込む「作者=神」の居場所がもはや存在しないことを宣言した
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら