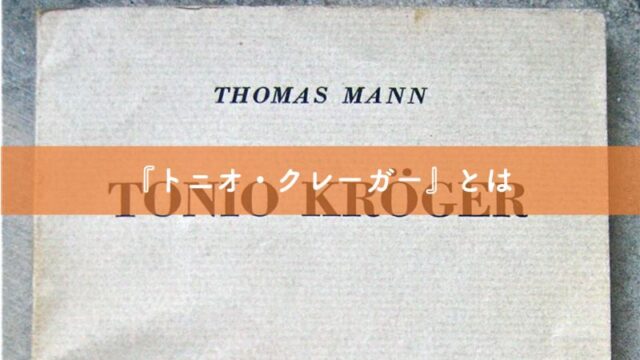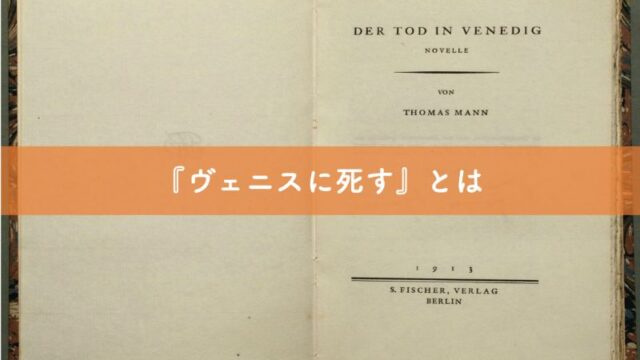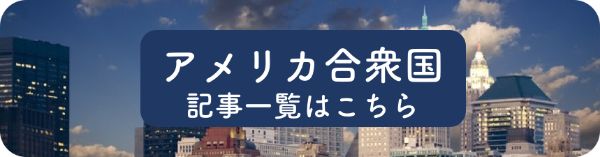カフカの『城』(英; The Castle, 独;Das Schloss)とは、カフカの最晩年に書かれた長編作品で、カフカ没後に発表された長編三部作のうちの一作です。マックス・ブロートの編集により1926年に出版されました。
カフカの『城』は『変身』『審判』と並び、代表作の一つです。また、語り手の視点と主人公Kの視点が一致している、いわゆる「語りの一元性」が見られる作品としても有名です。
この記事では、
- カフカの伝記的情報
- カフカの『城』のあらすじ
- カフカの学術的な考察
をそれぞれ解説しています。
好きな箇所から読み進めてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:カフカ『城』のあらすじ
1章ではカフカの『城』を「作者」と「あらすじ」から概観します。2章ではカフカの『城』に関する文学的な考察を解説しますので、あなたの関心に沿って読み進めてください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1: 『城』の作者紹介
まず、あらすじを紹介する前に、簡単に作者の紹介をしましょう。
端的にいえば、フランツ・カフカ(1883年 -1924年)とは以下のような人物です。
- 当時はオーストリア=ハンガリー帝国、現在でいえばチェコ共和国のプラハ出身である
- ユダヤ人の家庭に生まれる
- プラハの生まれであるため、周りの多くの人々はチェコ語を話していたが、カフカはドイツ語で教育を受け、創作もドイツ語で行なった
- 40歳という若さで亡くなった
文学的な評価でいえば、
- 戦前はナチスの文化政策の影響によってカフカの作品が読まれることがあまりなかった
- しかし戦後、カミュやサルトルなど、フランスの実存主義者が「不条理」という概念を用いて論じ、それ以来、世界的にカフカの文学が流行するようになった
という変化があります。
そのため、アルベール・カミュの『異邦人』などとならんで、カフカの『変身』や『審判』は「不条理の文学」と呼ばれたりします。
『変身』や『審判』に関しては以下の記事を参照ください。
現在でも村上春樹など、多くの作家に影響を与え、ジェイムズ・ジョイス(代表作『ユリシーズ』)やマルセル・プルースト(代表作『失われた時を求めて』)らと並んで、20世紀を代表する作家として世界的に評価が高いです。
1-2: カフカ『城』のあらすじ
カフカに経歴はこれまでにして、『城』のあらすじを紹介しましょう。以下のあらすじは前田敬作(訳)『城』(新潮文庫, 1971年)を参照しています。
測量士K
- 測量士Kはある城に管轄された村にやってきた。だがKは村に来てはじめて、測量士としての自分の仕事が必要ないことを知る
- Kは自分の立場を守るためにすこしでも城に近づこうとするが、村長との衝突、さらにはほとんどの村人や城から派遣された役人たちと反目してしまい、いつまでたっても城に近づくことができない
- こうして当初、名目的に測量士として村長から認められたKも最終的には仕事がなくなり、自分の立場が危うくなってしまうのであった。
女性の協力
- Kは他国から来たために、城の力や権力がどのようなものかわからず、村人がなぜそこまで城から派遣された役人や秘書たちを敬ったり、城の言いなりになっているのかが理解できない
- ただそのようなKを見かねて、幾人かの女性は協力してくれるようになる。城の役人クラムの手紙などを届ける仕事をしているバルナバスの姉であるオルガは、自分たちの経験について話し、Kに城の権力と村の状況についてわからせようとする
Kの結末
しかし、酒場娘のフリーダとのスキャンダルなど、様々な問題を起こしてしまったKは、結局自分の存在が村の中で自分が何も知らない子供のように右往左往し、ただ騒いでいるだけでしかないことに気づくのであった。
どうでしょう?大まかに物語の展開をつかむことはできたでしょうか?
- 『城』は語り手の視点と主人公Kの視点が一致している、いわゆる「語りの一元性」が見られる作品である
- カミュやサルトルなど、フランスの実存主義者が「不条理」という概念を用いて論じ、それ以来、世界的にカフカの文学が流行するようになった
2章:カフカ『城』の考察
さて、2章ではカフカ『城』の背景、学術的な見解について紹介していきます。
2-1: カフカ『城』の背景
そもそも、『城』はカフカ没後の1926年、ドイツ・ライプチィヒの出版社から出版されたものです。
カフカ没後、カフカの部屋を整理していた友人のマックス・ブロートは、自分あてのカフカのメモを発見します。カフカのそのメモには次のように書いてあったといいます2マックス・ブロート「最初の版のあとがき」(『決定版カフカ全集』5、新潮社、1981年)参照。
- 今までに発表した『判決』、『火夫』、『変身』、『流刑地にて』、『田舎医者』の五冊と物語『断食芸人』の出版は認める。といっても、これらの作品を引き続き増刷して欲しいわけではなく、自分の作品を将来に伝えて欲しくはない
- 上記で自分が認めたもの以外、手に入る限り全部のもの(原稿や手紙など)は早急に焼却してほしい
しかし、カフカ文学の素晴らしさにいち早く気づいたブロートはこのカフカの遺言に半ば背くような形で遺稿を整理し、随時カフカの作品を発表していきました。『城』もそのようにして発表されたうちのひとつです。
編集の際、当初、『城』の原稿全体には題名がついていませんでした。しかし、カフカが生前、ブロートなどに作品の話をするときに『城』と呼んでいたことから、ブロートが作品のタイトルを『城』と名付けました。
一応、作品はなかば完結した作品として読めるように、ブロートが作品の編集を行っているが、作品自体は未完の作品です。途中でカフカが『城』を書くこと自体をやめてしまったため、物語が途切れてしまうような形で終わってしまっているのが実情です。
また、『城』は『審判』と同じようにブロートによってタイトルが名付けられており、作品の章立てもカフカの構想をもとにしてブロートによって配列されています。しかし、次の点で『城』と『審判』には違いがあります。
- 『審判』が章立てに関して多くの批判や問題点が提起されている
- その一方で、原稿の中で章立てが指示されていたこともあって、『城』に関する編集上の問題点は『審判』ほどには指摘されていない3『城』の場合も批判がないわけではない
この背景をもとに、以下では作家論的解釈からテクスト論的な解釈まで、『城』がどのように評価されてきたのかについて簡単に解説します。
2-2: カフカ『城』の作家論的観点からの考察
まず、カフカが『城』を執筆し始めたのは1922年1月です。しかし、『城』執筆の前後のカフカの容体は決して好ましいものではありませんでした。
- 1917年に肺結核と診断され、以前から体調の悪かったカフカはたびたび仕事を休んで休養地で休暇を取っていた
- その時も現在のチェコとポーランドの境にある、リーゼンゲビルゲ山脈にある小さなホテルに滞在していた
- 『城』はそのホテルで執筆が開始され、約20日間そこに滞在した後、プラハに戻ってからも引き続き『城』の執筆が続けられた
- 同年3月なかばには、あるカフェでマックス・ブロートを相手に『城』の冒頭部分を朗読したとされる
- 同年6月、体調悪化によって務めていた労働者災害保健局を退職すると、7月下旬には南ボヘミアのプラニャという保養所に入り、そこで小説の執筆に集中するようになった
- しかし、その後徐々にペンが止まり始め、同年9月に執筆を中断。未完のまま、原稿だけが残され、この原稿は最終的に友人のマックス・ブロートの手に渡った
『城』執筆の前後における上記のようなカフカの状況は、彼の日記や手紙などによって明らかになっています。そのような資料をもとにして伝記的な研究が進み、作家論的に作品を解釈するために役立てられています。(作家論=作者の体験や経験にそくして作品を読んでいくこと)
たとえば、作家論的に解釈したとき、『城』では当時のカフカ自身の女性関係が随所に反映されているという解釈が可能になります。
カフカが『城』を書き始める前の1920年、ミレナ・イェセンスカと出会います。
ミレナ・イェセンスカ
- ミレナはウィーン在住のチェコ人ジャーナリストで、カフカの作品をドイツ語からチェコ語に訳す計画を抱き、カフカに接触している(実際に、ミレナはいくつかのカフカの作品をチェコ語訳した)
- カフカはそれ以前に二回の結婚と破局を経たあとであり、さらに当時も肺結核の療養中に出会った女性と婚約中であったが、その出会いがきっかけとなり、カフカは婚約を解消した
- ミレナは共産主義者としてナチスの強制収容所に送られ、そこで亡くなった
※ちなみに、カフカがミレナに宛てた手紙は、カフカの死後、『ミレナへの手紙』として刊行されています4日本語訳は池内紀(訳)『ミレナへの手紙』白水社、2013年。
実は二人が出会った当時、カフカも婚約中でしたが、ミレナにも夫がいました。二人とも不倫していたことになりますが、彼女はカフカを愛しつつも、夫のから離れることもまたできなかったといいます。
『城』に登場するフリーダはこのミレナの姿が反映されていると考えられています。また、ミレナの夫の姿も城の「X庁長官」として登場するクラムの人物像にいくらか影響を与えているとも言われています。
つまり、
- 当時カフカの交際していた女性はミレナであり、『城』では彼女との関係が作品のなかに反映されている
- 主人公Kと恋愛関係になるフリーダという人物の性格や彼女の周りにいる男性について、カフカとミレナ、そしてミレナの周りにいる男性の特徴が反映されている
と作家論的に解釈することができるのです。
2-2: 『城』の文学的な評価
次に、カフカの『城』を、
- カフカ文学の紹介者であり、カフカの友人マックス・ブロートによる解釈
- ノーベル文学賞を受賞した小説家であり実存主義者としても知られているアルベール・カミュによる解釈
からみていきましょう。
2-2-1: マックス・ブロートの解釈
結論からいえば、マックス・ブロートは、
『城』の「あとがき」において、『城』と『審判』の類縁性を指摘し、二つの作品が表裏一体の関係である
と述べています。(→カフカの『審判』はこちら)
戦前から戦後、さらには現在においても、ブロートの見解はカフカ文学の解釈のなかで最も有名なものであり、どのカフカ作品について言及するにしても、ブロートの見解を参照することが必須となってきます。
ブロートはカフカ文学全体を宗教的・ユダヤ教的視角から解釈しようとしており、『城』についても人間と神の関係から読み解こうとしています。
具体的に、マックス・ブロートは、以下のように『城』を解釈しています5「初版あとがき」(『決定版カフカ全集』6新潮社、1981年)を参照。
- 『審判』の場合、主人公ヨーゼフ・Kは被告として当局から追究をうけるが、反対に『城』ではKは城から排斥される。二つは正反対の関係にあるが、根本的感情では同一のものがある
- Kが入場を許されない城とは神の恩寵や裁きを意味しており、つまり、『城』で描かれているのは神性の二つの現象形式――裁きと恩寵――である。一方、村やそこで暮らす人々は、神に対する人間、あるいは人間の運命を表している
どうでしょう?ブロートの宗教的な解釈は腑に落ちるでしょうか?より詳しく知りたい方は、『決定版カフカ全集 6』(新潮社)をぜひ参照ください。
2-2-2: アルベール・カミュの解釈
戦後、サルトルやカミュなど実存主義者とよばれるフランスの知識人たちによって、カフカの文学が実存主義文学の先駆として取り上げられると、それ以後、カフカ文学は世界的な注目を集めるようになりました。
ここではカフカ文学を論じる上で重要な実存主義者の解釈について簡単に触れておきましょう。たとえば、アルベール・カミュはカフカ文学と『城』について次のように述べています6「フランツ・カフカの作品に於ける希望と不条理」(『シーシュポスの神話』新潮社、2006年収録)を参照。
アルベール・カミュ(1913年〜1960年)
- 自然らしいものと異常なもの、個人と普遍的なもの、不条理と論理など、これらの間を揺れ動く、普段の動揺がカフカの全作品に見られ、それが彼の作品にある種の響きと意味を与える
- カフカ文学は不条理さがその特徴であり、その不条理は絶対に克服されることはない
- しかし、そのような不条理な世界の中にも、『城』では特異な形の希望が導入され、Kが最後に神への恩寵の砂漠の中へ入ろうとする試みも見られる
こちらもよく詳しく知りたい方は、『シーシュポスの神話』(新潮社)がおすすめです。
2-2-3: 村上春樹の解釈
ちなみに、文学研究者ではないですが、村上春樹は自身の作品に影響を与えた作家の一人としてカフカをあげて、『城』についても次のように語ったことがあります。
- 2006年10月30日、チェコ・プラハで行われた「フランツ・カフカ国際文学賞」受賞式における受賞挨拶のために書いた草稿のなかで、カフカの作品や言葉に言及
- 村上は15歳の時にカフカの『城』を初めて読み、自分の心が二つに引き裂かれたように感じたという
- 「非日常的な、また時として落ち着かない『分裂』感を持ったまま、その本を読み終えた」。そこで感じた感覚が「僕の文学的原背景となったかもしれない」
- 『海辺のカフカ』にはその時に感じた感覚、カフカ的な世界が息づいている
村上春樹とカフカの関係を知るためには、たとえば、「凍った海と斧」(『村上春樹雑文集』新潮文庫、2015年収録)が有益です。
2-3: テクスト論的解釈
フリードリヒ・バイスナーはカフカ文学の特徴として、第三者的な視点から語り手が語っているのではなく、主人公自身が語り手の役割を引き受けていると指摘しています。
このような見解は第二次大戦後に実存主義者によって注目されたことから世界的なカフカ・ブームが巻き起こったあと、あらためてカフカのテクストをその構造や手法に注目して考察してみようという声があがり始めていた時期、1950年代前半に登場するようになりました7バイスナー『物語作者フランツ・カフカ』(せりか書房)を参照。
フリードリッヒ・バイスナー
- カフカ文学では語り手の視点と主人公の視点が一致している。これを「語りの一義性」や「語りの一元性」という
- 主人公の内面的世界がそのまま反映されているため、作品では現実と内面的世界がいりまじった世界が提示されている
- これは言い換えると、作者であるカフカ自身の内面世界が表現されているのである
バイスナーの指摘通り、『城』でも主人公・Kの視点が基本的に語り手の視点と一致しています。戦後のカフカ文学におけるテクスト論的な研究を促進した点で、バイスナーの見解は現在でも重要な位置を占めているといえます。
さらに、このバイスナーの見解を巡って、批判や新たな問題が提起され、その後もテクスト論的にカフカの文学が再検討されるようになりました。その結果、現在でも世界中で様々な視角から『城』の読解が試みられています。
- 作家論的解釈・・・当時のカフカ自身の女性関係が随所に反映されている
- ブロートの解釈・・・人間と神の関係を読み解く
- カミュの解釈・・・不条理な世界の中にも、『城』では特異な形の希望が導入される
- バイスナー・・・主人公自身が語り手の役割を引き受けている
3章:カフカ『城』の学び方
どうでしょう?カフカの『城』に関して理解を深めることはできましたか?
ぜひ、この記事をきっかけに原著に挑戦してみてください。
以下は深く学ぶためのオススメ本です。
有村隆広『カフカとその文学』(郁文堂)
カフカの生い立ちやこれまでにカフカが世界中でどのように論じられてきたのか、分かりやすくまとめられています。少し古い本であるが、読書案内などもついており、本格的に勉強したい方は手に取りたい一冊。
リッチー・ロバートソン『カフカ』(岩波書店)
イギリス・オックスフォード大学のドイツ文学者が書いたカフカ文学の入門書。文化史研究やジェンダー論的研究など新しい研究成果なども盛り込みながら、カフカ文学を優しく解説しています。
(2021/11/22 07:49:54時点 Amazon調べ-詳細)
森泉岳士『カフカの「城」他三篇』(河出書房新社、2015年)
カフカの「城」ほか、エドガー・アラン・ポー、ドストエフスキー、夏目漱石の作品を各16ページで漫画化。作品の世界をイメージしづらい方は漫画で予習するのもおすすめ。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 『城』は語り手の視点と主人公Kの視点が一致している、いわゆる「語りの一元性」が見られる作品である
- 作家論的解釈・・・当時のカフカ自身の女性関係が随所に反映されている
- バイスナー・・・主人公自身が語り手の役割を引き受けている
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら