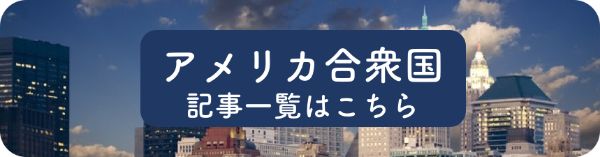家父長制(Patriarchy)とは、男性の女性に対する支配を可能にする権力関係の総体を指します。
ジェンダー論を学ぶ上で不可欠な概念ですので、その歴史から理論的貢献までしっかり理解する必要があります。
そこで、この記事では、
- 家父長制とヨーロッパ・日本
- 家父長制とフェミニズムの関係
などをそれぞれ解説していきます。
関心のある所から読み進めてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:家父長制とは
1章では家父長制を「意味」「ヨーロッパ」「日本」から概説します。フェミニズムとの関係を知りたい場合は2章からお読みください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:家父長制の意味
家父長制とは、一体どんな意味なのでしょうか?歴史的にいえば、以下のような意味が与えられている用語です。
- 家父長制は、もともとはキリスト教でノアの箱舟前後に生きていた家長(族長)を指す古い言葉であった
- その後、19世紀に文化人類学者によって原初の母権制が注目され、そこから段階発展的に移行するものとしての父権制(=家父長制)、という第二の意味が与えられた
- そして、1960年代の政治の季節から生まれた第二波フェミニズムの潮流におけるラディカル・フェミニズムによって、父から夫へ枠を広げ、年齢と性からなる男性たちによる女性たちの支配という第三の意味が与えられた
フェミニストにとって、家父長制は「男性支配」「女性たちの抑圧」とほぼ同義語として使われていましたが、家父長制には後者とは異なる明確な特徴がありました。
- 家父長制は制度であり、個人的関係、精神状態を指しているものではない
- 家父長制を資本主義に対立させた
つまり、家父長制の考えを手にすることによって、フェミニストは男性の支配と女性の服従の統合的な理論を打ち立てることが可能となりました。
すべての女性は、形は違ってもよく似た抑圧に苦しめられており、単に経済の仕組みを変えるだけではその抑圧をなくすことはできないということを認識することができるようになったのです。
ところが、この見解の違いによって、フェミニストは新左翼運動と対立するようになります。なぜなら、反資本主義を訴える新左翼運動にとって、女性の従属は資本主義のひとつの帰結にすぎないと考えられていたからです。
それゆえ、家父長制を資本主義とは区別されるひとつの自立した体制だと主張するフェミニストは、「資本主義を特権化している」として新左翼運動から痛烈な批判を浴びせかけられるようになります。
さらにフェミニズム内部でも、女性たちをしばりつけるのは「家父長制か資本主義か」、それとも「家父長制と資本主義か」を論点に、ラディカル・フェミニズム、マルクス主義フェミニズムを中心に重要な論争がくり広げられていきます。
それぞれのフェミニズムの立場に関して、以下の記事を読んでみてください。
→【ラディカル・フェミニズムとは】背景・特徴・運動をわかりやすく解説
→【マルクス主義フェミニズムとは】特徴から批判までわかりやすく解説
1-2:家父長制とヨーロッパ
つぎに、ヨーロッパにおける家父長制について見ていきます。近代を経て、どのような変化がもたらされたのでしょうか?
- 家父長制という用語への批判のひとつに、家父長制は超歴史的かつ超地理的な概念のため、普遍的・本質主義的な女性支配の肯定に使われてしまうのではないかという懸念がありました。
- 実際、家父長制は、男性による女性の支配システムと言い換えることができますが、その様態は固定的なものではなく、時代や状況を反映し大きく変化している点は押さえておきたいところです。
たとえば、ヨーロッパの家族史を描いた姫岡とし子は、伝統社会から近代社会への移行において、産業革命と市民革命のほかに、家族革命といっても過言ではない大きな変化が起きたと述べています2姫岡とし子 2008『ヨーロッパの家族史』山川出版社。
現在の私たちがイメージする家父長制的な家族とは、「父親のみが稼ぐ」「子どもはつねに愛される存在」「母性愛は本能である」「家族はプライベートな領域」という固定観念がありますが、それはほんの100年から200年前に確立された近代家族というひとつの歴史的類型に過ぎないのです。
※家族に関する研究は、家族社会学の記事が詳しいです。→【家族社会学とはなにか】研究概要から問題までわかりやすく解説
『<子供>の誕生』のフィリップ・アリエスが有名ですが、多産多死が特徴の伝統社会において、人びとは子どもに無関心でした。
子どもは7歳頃には「小さな大人」として労働共同体に組み入れられ、母性愛も存在していませんでした。共同体の干渉をつねに受け、家には奉公人として常に他人が同居しており、血縁家族集団というプライバシーは存在していませんでした。
ところが近代になると、子ども服やおもちゃが登場するなど「子ども期」が新たに発見され、子どもは親の愛情を注がれる存在になります。産業化の進展により職住分離が進み、職場と家庭という「公」と「私」の空間的な分離が、「男は仕事、女は家庭」という性役割意識を生むことになったのです。
たとえば、次のイギリスの事例を考えてみてください。
- 18世紀イギリスでは劣悪な環境下で働く労働者の健康維持が問題となり、1802年最初の工場法が成立した。以来、段階的に女性と子どもの保護政策が拡張されていく
- 保護の名のもとで女性と子どもは労働市場から排除され、男性労働者による労働市場の独占は作り出されていった
- そして、市場の外に生まれたのが近代家族であり、主婦であった
- 現在の私たちがイメージする、夫婦と親子の情愛と親密さによって特徴づけられる血縁家族は、このように、近代になってはじめて誕生し、各階級に定着していった
そして、近代の家父長制の最大の特徴は、性差は自然であるという考え方です。
それ以前のヨーロッパにおける男女の性差は、社会経済的な地位の取り決めによってなされていたため、男女間に厳密な境界線は引かれていませんでした。しかし近代以降になると、妻の夫への従属が、女性一般の「自然」や個人の自発的な「愛の倫理」によってなされると考えられるようになります。愛すべき「子ども」の誕生もこれとセットでした。
このように、フィヒテやルソーなどの啓蒙主義者によって、理性的人格の自由な展開という新しい市民社会の原理と矛盾しないかたちで、家父長制を貫徹させる論理が打ち立てられたのです。
そして、この「生まれながらにして」自然的性差があるというジェンダーの考え方は、女性の無権利状態を正当化し、家事や育児こそ女性の天職とみなす考えを浸透させていくことになりました3姫岡 同上 38頁。
1-3:家父長制と日本
つづいて日本の家制度について解説していきます。家制度は、日本の家父長制を考えるうえで欠かすことができません。どのような制度だったのでしょうか?
端的に言うと、家制度とは日本の伝統とされる家族制度のことを指し、それを体系的に法制度化したのが、明治民法(1898年施行)でした。
明治民法には、武士社会の家族理念をもとにした家制度が定められていました。家は「家名・家産・家業を基盤として、これらが超世代的に継承されることを目的とする集団」であり、家長である戸主とその家族で構成され、原則として戸主は男性でした。
家制度の内容
- 戸主にはその家族を統括するための強い権限が認められ、家産をすべて管理した。しかし一方で、両親、祖父母などの存続を最優先とする扶養義務や祖先祭祀、家名の存続と発展のための務めが課されていた
- 父のみが子どもの親権、家督相続権をもったが、妻にはこれらの権利はまったくなかった
- また妻には厳格な貞操義務が課され、妻の不貞は離婚原因となったが、夫の不貞は誰かの妻と姦通し、その夫が告訴して姦通罪で処罰されたときのみ離婚原因になるなど、家制度は、男女不平等な法制度だった
この家制度が大きく変化したきっかけは、日本の敗戦でした。1947年、日本国憲法の誕生に伴い明治民法は大きく改正され、家制度は廃止されることになります。この民法改正は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚し、民主化のシンボルとしてもてはやされました。
しかしそれから70年以上を経て、いまだに家意識や家父長意識を残した規定が残っているとの批判もあります。
具体的には、2009年8月国連の女性差別撤廃委員会は、民法733条(再婚禁止期間)や民法750条(夫婦同氏の原則)などについて、男女平等の観点から「即時改正すべき」と勧告しています。
2020年11月現在、報道やSNSなどで選択的夫婦別姓の議論が再燃していますが、民法の改正は、ライフスタイルの変化や国際的な視点からも急務の課題となっています4井上輝子ほか編 2002『岩波女性学事典』岩波書店 22-23頁, 461-463頁 ; 木村涼子ほか編 2013 『よくわかるジェンダースタディーズ』有斐閣 141頁。
- 家父長制は、ラディカル・フェミニズムの鍵となる考え
- 家父長制の意味は、男性の女性に対する支配を可能にする権力関係の総体
- 近代以降、家父長制的な家族のあり方が「自然」なものとされた
2章:家父長制とフェミニズム
2章では、家父長制についての代表的な論者を取り上げながら、具体的な思想や批判についてより詳しく見ていきます。
2-1:ケイト・ミレット
ここでは、家父長制という考え方に光を当てたケイト・ミレットの『性の政治学』(1970)について概観してみたいと思います5ミレット・ケイト 1970=1985『性の政治学』ドメス出版。ラディカル・フェミニズムの「個人的なことは政治的である」というスローガンの元となったこの本が描く家父長制の特徴は、一体どのようなものだったのでしょうか?
本書はケイト・ミレットの博士論文を書籍化したもので、雨後の筍のように主張が生まれ混沌とした状況にあった第二波フェミニズムに、はじめて理論的根拠を提供し、女性たちに「バイブル」として熱狂的に迎えられた1冊でした6ミレット・ケイト 1970=1985『性の政治学』ドメス出版 624頁。
内容を概観すると、以下のようになります。
第一部ではヘンリー・ミラーの『セクサス』、ノーマン・メイラーの『アメリカの夢』、ジャン・ジュネの『花のノートルダム』の三作品についての文芸批評を行っており、男性作家によるセックスの描写をとおし、男女間の権力構造を丹念に描き出している
第二部の「歴史的背景」では、第一波フェミニズムの展開、ナチス・ドイツとソ連という国家による家族操作の事例、「女」というイデオロギーについて論じている
第三部は文学における「性の政治」に光を当てており、ミラーとメイラーに共通するのは、性的・文学的動機としてミソジニー(女性嫌悪)の文学的伝統、さらには「性革命」への嫌悪があると述べる
そして最終章でジャン・ジュネ論が展開され、同性愛間における支配秩序を見つめることで、男女間による権力構造を逆照射し、ジュネの文学世界の革新性を導き出す
では、ミレットが打ち出した家父長制とはどのようなものだったのでしょうか?彼女が家父長制を定義する際に連想したイメージは父(patri)の支配(archy)で、ミレットは家父長制を、年齢と性による二重の男性支配のシステム全体であると定義しました7ミレット 同上 72頁。
ミレットの家父長制概念は、バッハオーフェンの『母権論』とヘンリー・メインの『古代法』の原始家族支配形態をめぐる文化人類学の論争を踏まえたうえで再定義されたものでした8井上ほか編 同上 79-80頁。
このミレットの定義に対し、もっとも手厳しい批判を与えたのは新左翼でした。なかでも代表的な論者はジュリエット・ミッチェルで、政治体制は特定の生産様式に依存するというマルクス主義の立場から、家父長制は永続的な性格をもつが生産様式ではなく、経済に対して支配的な決定を下しているわけではないと批判しました9江原由美子・金井淑子編 2002『フェミニズムの名著50』平凡社 98頁。
さらに本書全体について「バラバラなメカニズムのランダムな指摘に終わっている」10ミッチェル、ジュリエット 1971=73『女性論』98頁と手厳しく批判されましたが、ミレットの分析がマルクス主義の立場に立つ女性たちに大きな衝撃を与えたことは間違いなく、女性たちの視点からマルクス主義の再解釈をうながすきっかけとなりました。
本書の最大の力点は、
「セクシュアリティ」「恋愛」「婚姻」「母性」「子育て」「家族」「性暴力」など、現在もビビッドに取り扱われる個別課題をいとぐちに、家父長制という巨大な抑圧装置の構造を解き明かすこと
でした。
これこそが「個人的なことは政治的である」という第二波フェミニズムのスローガンにつながっていくのです。
冒頭の「日本語版への序文」では、大学への就職活動がうまくいかなかったミレットが1961年から2年間滞在した日本での経験が綴られており、不遇な状況下における日本の女性たちをまなざす彼女の熱意と分析眼に触れることができます。
2-2:シュラミス・ファイアストーン
つづいて、ミレットの家父長制という問題提起を引き継いだフェミニストの考えを見ていきましょう。
まず、『性の弁証法』(1970=1972)を書いたシュラミス・ファイアストーンは、家父長制の起源を解明しようと試みました11シュラミス・ファイアストーン 1970=1972『性の弁証法』評論社。その議論をまとめると、以下のようになります。
- ファイアストーンは、家父長制の起源を生物学的家族という基本的生殖の単位にあるとする
- この生物学的家族こそが、社会の普遍的で基礎的な単位とされてきたからこそ、妊娠、出産機能をもつ女性は、この単位に拘束され、社会は不平等な二つの生物学的階級に分断されたのだと主張した
- 要するに、この性階級こそ、すべての階級制度の根源であり、すべての歴史の基礎であるという論理を打ち出した
ここからが面白いのですが、ファイアストーンは、家父長制を廃絶するためには、プロレタリアートによる革命と生産手段の独占が必要なように、下級階級(女性)による生殖のコントロールの掌握と肉体の所有権の回復が必要であると論を展開します。そこで重要になってくるのが科学技術です。
科学技術の重要性
- 科学技術が進歩すれば、男女の生殖機能の差は文化的に重要でなくなり、女性は妊娠という「野蛮な」重荷から解放される
- 人工生殖は、男性も子どもを持つことを可能にし、育児も平等に行われ、女性だけが人類のために子どもを産むという現実を変えていくであろう
さらにいえば、工場(!)での再生産も可能になるかもしれません。その際はもはや家父長制的核家族という生物学的家族は支配的ではなくなり、男の女に対する、大人の子どもに対する権力心理も消滅し、女だけでなく子どもも解放され、人種差別の根拠もなくなるだろうとSF級の未来を展望するのです。
このファイアストーンの主張に対し、生物学的偏向、没歴史的偏向、楽観的な科学技術信仰などの批判が浴びせかけられました。
しかし、ファイアストーンやミレットをはじめとするラディカル・フェミニストは、マルクス主義が階級抑圧の解消を社会全体の解放としてとらえているのと同様に、女の解放を、すべての人間の人間性を回復する社会変革の鍵として位置づけ、新しい社会運動や黒人解放運動との連帯を訴えました12江原由美子・金井淑子編 1997 『ワードマップ フェミニズム』新曜社 25-27頁、江原・金井編 2007 同上 101−109頁。
2-3:ジュリエット・ミッチェル
アメリカの代表的なラディカル・フェミニストであるミレットとファイアストーンの理論を批判的に継承し、発展させたのがイギリスの精神分析医・ジュリエット・ミッチェルでした。
彼女が世に出たのは1966年に『ニュー・レフト・レビュー』で発表した論文、「女――もっとも長い革命」において、はじめてマルクス主義とフェミニズムの理論的な結合を試み、マルクス主義フェミニズムの理論的地平を切り拓いたのがきっかけです。
上で述べたように、ミッチェルはミレットの家父長制概念を痛烈に批判して、家父長制はそれ自体生産様式ではないと述べます。そしてファイアストーンの議論は没歴史的であるとし、ある特定の社会における家父長制の働きを歴史的・文脈的に見ることの重要性を訴えました13ジュリエット・ミッチェル 1971=1973『女性論』合同出版。
一方で、ファイアストーンの女の抑圧の根源としての家族という論点を評価します。そして、家族にあらわれる生物学的なものと社会的なものとの境界を見極めるために、精神分析が有効であると訴えます。それはどういうことでしょうか?簡潔にいえば、以下のとおりです。
- ミッチェルは『精神分析と女の解放』(1974)で、家父長制の焦点を「父の法」すなわちファルス中心主義に定め、フロイト理論を応用しながら近代の核家族に現れるエディプス・コンプレックスを問題化した
- つまり、資本主義的家族における家父長制というイデオロギー様式を、資本主義という生産様式から独立させることによって、家父長制と資本制の相互依存関係を明らかにしようとした
しかし、このマルクス主義と精神分析を用いた家父長制分析の接合の試みは、成功しているとは言い難いとの指摘もあます。
というのも、もっぱら家父長制を意識、文化のレベルに置き、結局家族を社会の外側に位置づけるというミッチェルの理論は、ラディカル・フェミニズムが性差別の根源として批判してきたはずの、近代特有の二元論、すなわち「公」と「私」の分断を克服できていないではないか、という批判です。
とはいえ、ミッチェルの理論が、ナンシー・チョドロウをはじめとする精神分析を用いた性差、ジェンダー研究に発展したことは間違いありません。さらに、資本制と家父長制の一元論を訴えたハイジ・ハートマンや家内制生産様式から家父長制を見出したクリスティーヌ・デルフィ、国際分業における性別分業を焦点化したマリア・ミースなど、マルクス主義フェミニズムの理論的な発展に大きく貢献することになりました。
- 20世紀以降、家父長制概念に光を当てたのはミレットの『性の政治学』である
- ファイアストーンは女性の妊娠、出産機能こそが女性抑圧の起源だとした
- ミッチェルは精神分析を用いながら、家父長制と資本制の相互依存関係を問うた
3章:家父長制を学ぶためのおすすめ本
家父長制に関して理解は深まりましたか?以下ではさらに理解を深めるための書物を紹介します。
難しさ★★★ ケイト・ミレット『性の政治学』(ドメス出版).
ラディカル・フェミニズムに理論的基盤を与えたバイブルとも称される一冊。文芸批評と文化批評を織り交ぜながら、家父長制に鋭く切り込んでいます。日本語版への序文は必読。
難しさ★★★ シュラミス・ファイアストーン『性の弁証法――女性解放革命の場合』(評論社)
ファイアストーンが25歳のときに2、3ヶ月で書き上げたという大胆でスリリングな一冊。女性の抑圧は生殖機能にあるとし、子宮の外での生殖による解放をイメージしました。
難しさ★ 姫岡とし子『ヨーロッパの家族史』(山川出版社)
多産多死の伝統社会から近代を経て、家族と子育てのあり方の変化が丁寧に描かれており衝撃的。近代という時代区分がいかに現代人を形成したのかを知るために重要な一冊。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
Amazonオーディブル無料体験の活用法・おすすめ書籍一覧はこちら
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 20世紀以降、家父長制概念に光を当てたのはミレットの『性の政治学』
- 家父長制は、男性の女性に対する支配を可能にする権力関係の総体のこと
- フェミニストは「自然」とされた近代家族のあり方に異議を唱え、家父長制と資本制との関連を問うた
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら