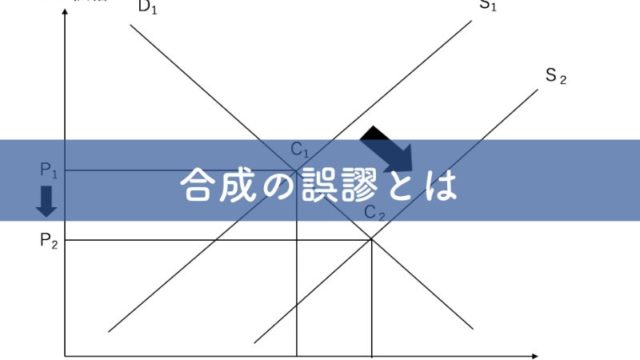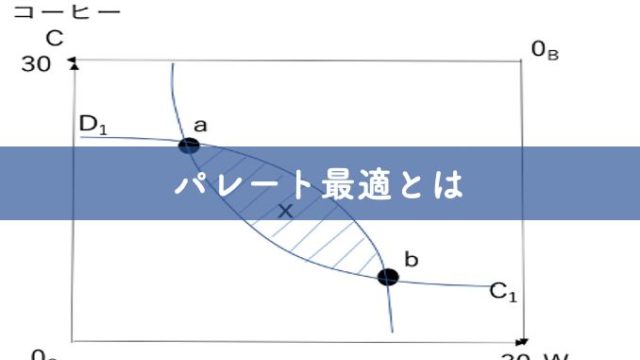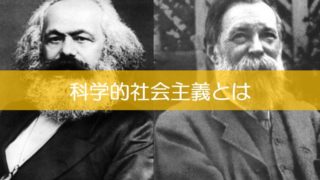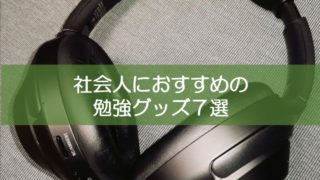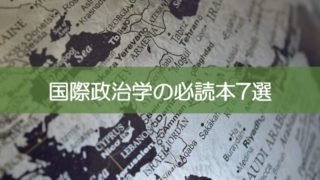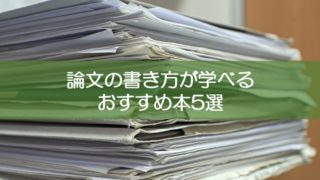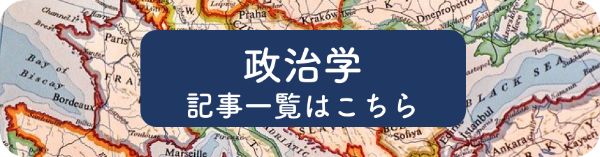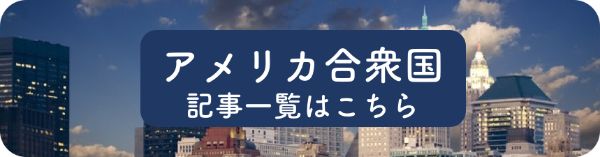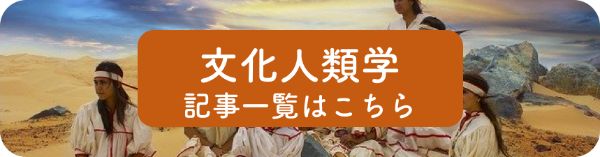情報の非対称性(information asymmetry)とは「ある情報や知識を一部の主体だけが私的で持ち、他の主体が持たない状態」1奥野正寛『ミクロ経済学入門』 日本経済新聞出版社, 32頁を指します。
定義的な説明だけではわかりにくいかもしれませんが、私たちは日々の経済活動で経験しています。
この記事では、
- 情報の非対称性の意味・問題
- 情報の非対称性の解消法
をそれぞれ解説します。
好きな箇所から読み進めてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:情報の非対称性とは
1章では情報の非対称性を概説します。対処法を知りたい方は、2章から読み進めてください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注2ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1: 情報の非対称性の意味
冒頭の確認となりますが、情報の非対称性とは、
「ある情報や知識を一部の主体だけが私的で持ち、他の主体が持たない状態」3奥野正寛『ミクロ経済学入門』 日本経済新聞出版社, 32頁
を指します。
経済学では、経済活動をおこなう主体は財やサービスと取引するための知識や情報をすべて有しており、常に合理的な判断をもって取引をおこなうと想定されています。
このような経済的合理性のみに基づいて行動する人間像は「経済人」と呼ばれ、古典経済学から近代経済学まで数多くの経済主体のモデルとなっています。
しかし、現実では取引に関するすべての知識や情報を保有した状態で活動をおこなうことは至難の業であり、あらゆるケースで人々は不確実性を考慮した取引をおこなっています。
簡潔にいえば、情報の非対称性とは、取引の不確実性のひとつの原因となる「経済主体間の情報量の差」に着目した論点です。
1-2:情報の非対称性の問題
買い手と売り手の情報の対称性が維持されることは、適切な経済活動をおこなうためにとても重要な条件です。
なぜならば、
- 売り手は、買い手のもつ情報を完全に把握することで、適切な財やサービスの提供が可能となる
- 買い手は、売り手のもつ情報を完全に把握することで、期待通りの満足が得られる取引をおこなうことができる
からです。
そして、こうした明快でシンプルな取引が実現できれば、経済的な無駄が発生せず、特定の経済主体の不都合を生まないような望ましい競争市場が実現できると考えられています。
逆に、買い手と売り手の情報量に差がある、つまり情報の非対称性が生じている状態では、競争市場の自律的な機能は阻害されて「市場の失敗」を生み出す原因のひとつとなります。
機能を阻害された市場では、本来、市場が有する資源の最適分配機能や自律的な価格メカニズムがうまく働かなくなり、社会全体に対する不経済が生まれます。
ゆえに、情報の非対称性を解消するためには、買い手と売り手の情報量の差を埋めることを目的とした政府の市場介入や情報公開制度の構築が求められます。
奥野の『ミクロ経済学入門』(日本経済新聞)は経済学の入門書として極めて有益です。情報の非対称性に関しても詳しいです。
(2020/11/16 19:07:55時点 Amazon調べ-詳細)
1-3:レモン市場と逆淘汰
そもそも、「情報の非対称性」という用語は、アメリカの経済学者ジョージ・アカロフ(George Arthur Akerlof)によって提唱されたものです。中古車市場で購入した中古車は故障しやすいとされた当時の事象のメカニズムを解明する論文で登場しました。
アカロフは、故障しやすい中古車を、英語のスラングで役にたたない欠陥品という意味を持つ「Lemon」という単語であらわし、以下で説明する事象が起こっている市場を「レモン市場」と命名しました。
- 個体ごとに使用年数や損傷の有無などが異なる中古品市場は、新品のみを取り扱う市場とは異なる特徴を持つ
- 新品のみを取り扱う市場では、売り手の供給する財の品質や性能は一定であり、財に対する情報も信頼性が高くなる
- しかし中古品市場では、中古品取引において特定のルールや基準がない場合、中古品の状態は、一般的に売り手の主観や経験によって決められ、財の品質や性能は取り扱う売り手によって変化する
たとえば、売り手がその中古品を新品に近い状態であると判断し、相応の価格をつけて販売したとします。すると買い手は、その中古品を売り手の説明通りの新品に近い状態だと判断し、購入を決めるでしょう。
しかし、実際に商品を使ってみると自分が思っていたよりも損傷や摩耗が激しいことに気づき、とても新品に近い状態ではないと思うかもしれません。この現象はまさに、当事者間での商品に対する情報量の差に起因するものです。
そのため、
- 売り手が単なる認識の違いで中古品の査定を間違えたのか、あるいははじめから悪意をもって買い手を騙そうとしたのかはさておき、同様のケースが続けば、買い手は中古品市場から離れていくことになる
- そして、次第に取引そのものが行われなくなっていき、いずれは市場そのものが機能しなくなる可能性がある
といえます。
また、レモン市場では、望ましくないものが望ましいものを駆逐する「逆淘汰(逆選択)」という固有の現象が起こります。
逆淘汰は、自然界では優生な種が生存競争を勝ち抜き、劣性の種が自然淘汰されるのに対して、レモン市場では不良なものが優良なものを淘汰してしまうことで、本来とは逆の生存競争が起きてしまうことに由来しています。
中古品市場の例においても、仮に流通する大多数の商品が買い手の期待を満たす品質を確保できていたとしても、そのなかに少数の劣悪な商品が存在していた場合、その品質の差を判別できない買い手は中古品市場での取引をためらうようになります。
すると、大多数の優良な商品を提供する売り手は正常な経済活動ができなくなり、市場からの退出を余儀なくされます。また劣悪な商品を提供する売り手のなかには、優良な商品を提供する売り手の評判に便乗し、本来の品質よりも割高な値段で商品を提供する者も出てくるでしょう。
その結果、市場には劣悪な商品ばかりが出回るようになり、逆淘汰の起きた市場は長期的には成立しなくなります。
1-4:情報の非対称性とモラルハザード
さて、逆淘汰についても更なる解説を含めながら、買い手と売り手の「取引後」の情報量の差によって市場がうまく機能しなくなるモラルハザードについて別の例を用いて解説します。
モラルハザードとは、下記のことを指します。
「情報の非対称性が存在するために、社会や組織にとって望ましくない経済活動の水準が(非効率的な経済活動が)選ばれること」4奥野正寛『ミクロ経済学入門』 日本経済新聞出版社, 211頁
逆淘汰では、取引前の情報の非対称性によって市場がうまく機能しなくなることを説明しましたが、モラルハザードは取引後の情報の非対称性により市場がうまく機能しなくなります。
では、保険業界を例にとって情報の非対称の問題を考えてみます。ここでは、説明をわかりやすくするために医療保険を例に挙げて解説していきます。
保険は、通常の財やサービスの取引とは性質が異なり、未来のリスクに対する備えという一種の情報を買うものであり、現実の財やサービスは存在しません。ゆえに、取引においては両者の持つ情報が大きな価値を持つことになります。
- まず取引前では、売り手(保険会社)は買い手(保険の加入希望者)に対して適正な保険料を設定するために買い手の持つ情報を収集する
- たとえば、過去に大病を患い入院した事実があれば、今後も病気になる可能性が高いと判断され、設定される保険料は高くなるし、これまで通院も入院もないのであれば保険料は安くなる
- しかし、この判断はあくまで表立った事実によるものに限られ、買い手のすべての情報を収集できているわけではない。たとえば、健康に対する意識が高く、食生活や運動習慣も管理できている人と、健康に対する意識が乏しく、食生活や運動習慣を全く管理していない人では未来の病気に対するリスクは異なる
- しかし、売り手が買い手のこうした情報を正確に収集することはとても難しい。なぜなら、健康への意識は主観的な要素が強く、個人の体質によっても病気のリスクは大きく異なってくるため、統一的な基準を設けることができないためである
- また、不健康な生活を送っていると思っている人であっても、少しでも保険料を安くしたいがために、虚偽の申請をしてくる可能性も考えられる
このような状況であると、売り手が買い手の持つリスクを正確に判断することが不可能である限り、売り手は病歴を持たない買い手に対しても平均的な保険料を設定せざるを得ません。
すると、壮健な人にとっては割高で、病気がちの人にとっては割安な保険料となってしまう事態が起こります。その結果、健康に自信のある人は、次々に保険への加入を見合わせ、保険料が一段と高まる逆淘汰が発生します。
このように、取引開始前の情報の非対称性は「逆淘汰」の問題を引き起こしますが、他方で、取引開始後の情報の非対称性は、これとは異なる問題を生み出します。
再び上記の例を用いて説明すると、病気になった時のリスクに備えて保険に加入した健康な人であっても、保険に加入したことで、万が一病気なっても大丈夫と考えてしまい、健康的な食生活や運動習慣をやめてしまうケースが考えられます。
もっと極端な例では、高額な保険金を目当てにわざと病気や怪我のリスクを負おうとする人も現れるかもしれません。しかし特別な事情がない限り、売り手は、買い手のこうした行動を監視・把握することはできません。
つまり、取引後であっても買い手と売り手の間には新たな情報の非対称が発生します。病気に備えた保険が、病気を誘発する要因になってしまえば、まさに本末転倒です。経済学では、この現象を「モラルハザード」と呼びます。
ここまで情報の非対称性がもたらす不確実性が市場にどのような悪影響をもたらすかを中心に解説をしてきました。次章では、こうした情報の非対称性による不確実性に対処するための具体的な方策について述べていきます。
- 情報の非対称性とは「ある情報や知識を一部の主体だけが私的で持ち、他の主体が持たない状態」5奥野正寛『ミクロ経済学入門』 日本経済新聞出版社, 32頁を指す
- 買い手と売り手の情報量の差を埋めることを目的とした政府の市場介入や情報公開制度の構築が必要となる
- 取引前後の情報の非対称性により市場がうまく機能しなくなる場合がある
2章:情報の非対称性に対する解消法
さて、2章では情報の非対称性を解消するための3つのアプローチを紹介します。
2-1: シグナリング
シグナリングとは、
優良な売り手がその優良性をなんらかの方法でアピールする方法
です。
たとえば、企業の宣伝でよく見られる「創業○年」という謳い文句は、多くの人が長年評価しているものという印象を消費者に与えることで、自社の優位性を間接的にアピールしています。
また、商品やサービスに対する「○年連続売上ナンバーワン」といった表示も、過去の実績をもとに消費者に自社の商品やサービスの優位性をアピールすることができます。
このように過去の実績を用いたシグナリングは、一定の期間営業を継続できている企業にとって非常に効果的なアピールであると言えます。
また、過去の実績を用いなくても、有名人を使ったCMや宣伝広告をおこなったり、大都市の商業地に旗艦店となる店舗を構えたりすることも、消費者に対して自社の商品やサービスの優位性をアピールできる点でシグナリングであると考えられます。
2-2: スクリーニング
スクリーニングとは、
情報を持たない買い手が売り手に対していくつかの選択肢を提示し、それを売り手に選択をさせることで情報の非対称性を解消しようとする方法
です。
1-4で用いた保険業界の例を用いて説明すると、買い手(保険加入希望者)が保険に関して希望する条件のみを売り手(保険会社)に伝え、その条件に合った保険を売り手側から提案する方法が考えられます。
この手法によって、買い手は自らの希望に合った保険プランを選ぶことができ、売り手も顧客の要望に合わせた細かい保険プランを複数用意することで、買い手の実態とそぐわない保険プランを提供してしまうリスクを軽減することができます。
スクリーニングは、売り手が主体的に行動するシグナリングと異なり、買い手に主体的な行動を求めることで、情報の非対称性の解消を見出すことに大きな特徴があります。
2-3: 制度と認証
制度と認証とは、
制度や認証をもとにした第三者の介入によって売り手と買い手の情報の非対称を解消しようとする方法
です。
たとえば、保険会社を設立するには、保険業法に定められている書類を金融庁に提出し、金融庁担当者との折衝を経て、内閣総理大臣の認可を得る必要がありあす。
その結果、
- 保険という現物を伴わない商品の取引において、国の認可という後ろ盾を利用することができる
- 売り手は公然に認められた商品を堂々と販売することができ、買い手は安全性や信頼性の高い商品を購入することができるようになる
といえます。
つまり、この保険業法の存在によって、保険市場は買い手か売り手のいずれか一方が有利にならないような公平性が整備され、取引における透明性を確保されています。
また、優良な売り手を第三者が指定する認証制度も有効です。たとえば、厚生労働省では、労働者が働きやすい環境づくりに積極的に取り組む企業に対して独自の認定を与える制度を用意しています6厚生労働省「認定制度とは」を参照。
この制度によって求職者は、就労希望先の雇用環境というブラックボックスに対しても、第三者の客観的な評価を参照できることで、雇用後のミスマッチを少しでも解消し、雇用環境における市場の失敗を未然に防ぐことができます。
もちろん、企業としてはこの認証を得ずとも求人活動をおこなうことはできますが、認証を得ることで優秀な人材を確保できる可能性が高まることから積極的に認証を目指す企業は増えています。
- シグナリングとは、優良な売り手がその優良性をなんらかの方法でアピールする方法である
- スクリーニングとは、情報を持たない買い手が売り手に対していくつかの選択肢を提示し、それを売り手に選択をさせることで情報の非対称性を解消しようとする方法である
- 制度と認証とは、第三者の介入によって売り手と買い手の情報の非対称を解消しようとする方法である
3章:情報の非対称性に関するおすすめ本
情報の非対称性の理解は深まりましたか?
この記事で紹介した内容はあくまでもほんの一部にすぎませんので、ここからはあなた自身の学びを深めるための書物を紹介します。ぜひ読んでみてください。
オススメ度★★★ 江口匡太『大人になって読む経済学の教科書』(ミネルヴァ出版)
数値やグラフを使わずに、経済学の用語がわかりやすく解説されています。情報の非対称性の事例も豊富であり、経済学を知らない方にもおすすめの1冊です。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 情報の非対称性とは「ある情報や知識を一部の主体だけが私的で持ち、他の主体が持たない状態」7奥野正寛『ミクロ経済学入門』 日本経済新聞出版社, 32頁を指す
- 取引前後の情報の非対称性により市場がうまく機能しなくなる場合がある
- 情報の非対称性を解消するための3つのアプローチがある
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
引用・参照文献
- 奥野正寛『ミクロ経済学入門』(日本経済新聞出版社)
- 江口匡太『大人になって読む 経済学の教科書』(ミネルヴァ書房)