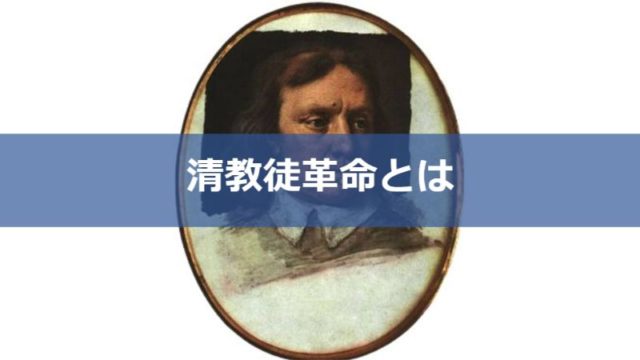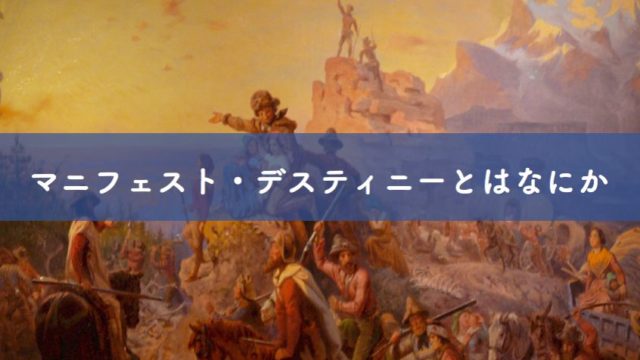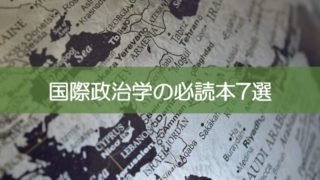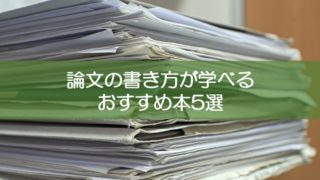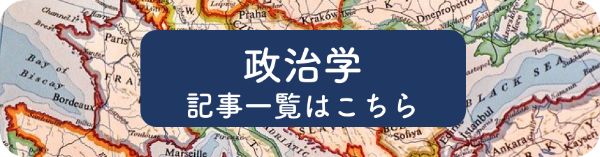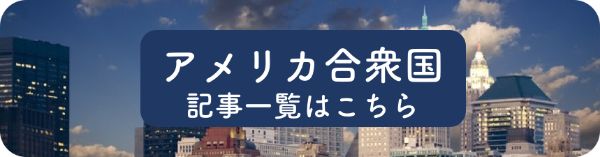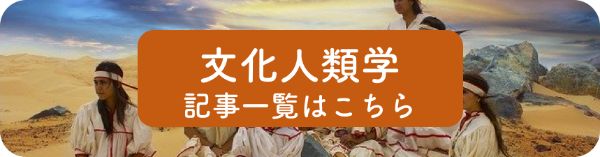富国強兵とは、幕末から明治にかけて、欧米列強と対等になるため日本が掲げたスローガンです。この方針の下行われたさまざまな政策を通じ、日本は大きく変化していくこととなりました。
富国強兵は現代日本社会を理解する上で、極めて重要です。身体技法から意識まで、富国強兵によって大きく変化したからです。
そこで、この記事では、
- 富国強兵の概要と具体的な政策
- 富国強兵の展開がその後に与えた影響
について解説します。
好きな箇所から読み進めてください。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:富国強兵とは
はじめに富国強兵の定義と、具体的な政策について紹介します。
全国歴史教育研究協議会編『日本史用語集』を見てみると、富国強兵の項目には次のように記されています1全国歴史教育研究協議会編『日本史用語集』(山川出版)232頁。
明治初期の国家目標。欧米列強に肩を並べるため、経済発展と軍事力の強化による近代国家の形成を目標とし、スローガン化した。
この説明に示されているように、富国強兵は近代国家を形成するため行われた一連の政策をまとめた名称であり、その具体的な政策は多岐にわたります。
もともと、「富国強兵」は春秋戦国時代に中国で唱えられた言葉で、日本でも明治以前から用いられていました。しかし今日の日本では、一般に「富国強兵」は明治期に行われた各種政策のことを指して用いられます。
詳しくは後述するように、富国挙兵の方針の下、徴兵制の実施や殖産興業のような経済振興策以外にも多くの政策が推進されています。それぞれの政策がどのような影響を及ぼしたのか知ることが、富国挙兵の実態を理解する上で重要なポイントとなります。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注2ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:富国強兵の意味・背景
上述の通り、もともと富国強兵と言う言葉は春秋戦国時代の中国で作られました。そして日本でも19世紀に欧米列強の圧力が強まる中で、さまざまな論者によって唱えられるようになっています。
たとえば、安政4(1857)年、欧米列強との貿易が始まる直前に幕府老中の堀田正睦が、今後の日本の採るべき方針について次のような意見書を記しています3千葉県企画部県民課編『堀田正睦外交文書』(ホマレ印刷,1981)16-17頁。
〔前略〕方今第一の専務は、国力を養い士気を振起せしむるの二事に止まるべく候へ共、総じて強兵は富国より生じ、富国之基〔もとい〕は貿易互市を以て第一となす故、〔中略〕広く万国に航し貿易を通じ彼が所長〔注.欧米各国の長所〕を採り、此の不足を補い国力を養ひ、武備を壮〔さかん〕にし〔後略〕
(注.適宜句読点を補い、字体を現用のものに改めた)
ここで堀田が述べているように、幕末の日本では欧米列強との貿易を通じ、国力を養い武備を備えることが急務と考えられていました。そして、この方針を示す語句として、幕末にはさまざまな論者が富国強兵を唱えるようになりました。
事実、前述の堀田だけでなく、薩摩藩のような雄藩や尊王攘夷論者たちも富国強兵を提言しています。
このように富国強兵の必要性は、幕末には幅広い層で共有されるようになっていました。そして明治政府もさまざまな政策を通じ、富国強兵の実現を目指すこととなったのです
1-2:富国強兵の具体的な政策
ここでは富国強兵を実現するため実施された、代表的な政策の概要を紹介します。
1-2-1:税制の改革
江戸時代、幕府の主な収入源は年貢でした。しかし年貢は米価の変動や収穫量によって収入が左右されてしまうため、財源を安定させることが難しかったと言われます。
そこで明治政府は富国強兵の財源を確保するため、税収を安定させるために税制改革を行いました。
税制改革の概要
- 1871年に「田畑永代売買禁止令」を廃止し、地券を交付して農民の土地所有を認めた後、1873年に「地租改正条例」を公布して、全国で土地の測量を開始した
- 一連の政策の目的は、所有する土地の面積や収穫量に基づいて地価を算定することであった
- 政府は土地所有者に地価の3パーセントを地租として金納することを義務付け、年貢よりも安定した税収を確保しようとした
政府は地租改正と並行して、印紙税や地方税なども創設しています。その後も、さまざまな税が創設され、明治末年までに所得税や酒税、煙草税のように今日にいたる近代的な租税も開始されました。
このように財源確保のための税制改革によって、今日の税制の原型が作られたのです。
1-2-2:殖産興業
政府は地租改正事業などを通じて確保した税収をもとに、経済振興政策も進めています。政府が行った一連の経済振興策は、「殖産興業」と呼ばれています。
殖産興業の概要
- 1870年、政府は殖産興業を推進する官庁として工部省を設置した後、各地に官営の造船所や鉱山、工場を設立して工業化を推進していった
- その代表的な事例が、1872年に群馬に設立された富岡製糸場である。富岡製糸場を中心とする養蚕施設は、2014年に「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産にも登録されている
このような官営工場の設立と並行して、政府は「お雇い外国人」を招聘し、彼らの指導の下で近代的な産業の育成を図りました。
同時に、1872年に新橋・横浜間で鉄道が開通したのを皮切りに鉄道の敷設が進められ、産業を支えるインフラの整備も進められていきました。
1-2-3:学制の発布
1872年、政府はフランスの制度を参考に「学制」を公布して、近代的な学校教育制度を整備しています。その際に発された太政官布告で、政府は教育の目的について次のように述べています4文部省内教育史編纂会『明治以降教育制度発達史』第一巻(竜吟社,1938)276-277頁。
〔前略〕士官農商百工技芸、及び法律政治天文医療等に至る迄、凡人の営むところの事、学あらざるはなし。人能く其才あるところに応じ、勉励して之に従事し、しかして後、初めて生を治め、産を興し、業を昌にするを得べし〔後略〕
(注.適宜句読点を補い、字体を現用のものに改めた)
ここで政府は、産業や医療、行政に従事する人材は、それにふさわしい学問を修めなくてはならないと述べています。富国強兵のためにはこれらの諸分野の発達が不可欠であり、そのために政府は、一定水準の能力を身に付けた人材を大量に育成することを目指していたのです。
学制公布当時、政府は全国を8つの大学区に分け、各大学区を32の中学区、各中学区を210の小学区に分けることを想定していました。そしてこの想定に基づき、全国に8つの大学と256の中学校、約5万4000の小学校を開設する計画が示されています。
明治以前、庶民の教育は主に寺子屋や筆書所が担っていました。これらの施設では学習内容が個々人で異なり、教師は子どもに合わせて個別指導を行っていたようです。
しかし学制に基づく学校教育では、一定の能力を身に付けた人材を大量に確保するため、定められた科目を時間割に沿って学ぶ一斉授業が行われるようになりました。この授業形態はその後も踏襲され、今日まで続くこととなります。
1-2-4:徴兵制の実施
富国強兵を実現する上で、兵制改革は最も重視された改革の1つです。政府は1872年に「徴兵告諭」を出した後、1873年には「徴兵令」を公布し、それまでの武士に頼った軍事力を改め、国民皆兵の軍隊を保有することを目指しています。
ただし国民皆兵とはいえ、明治初期の段階では全員が兵士になったわけではありません。歴史学者の牧原憲夫は、以下のような指摘をしています5『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』138頁。
- 20歳になった男性は徴兵検査を受けることとなっていた
- そして検査に合格した者の中から、クジによって入営者を決めた
- 文字通りの国民皆兵は、日清戦争の頃まで実現することはなかった
徴兵令が出された時点では、東京・大阪・名古屋・広島・熊本・仙台の6か所に鎮台が設置されており、徴兵された人々は居住地域を管轄する鎮台に配属されています。
その人数は全国で約1万人程度でしたが、兵士となった者は除隊後も予備役・後備役となり、有事には真っ先に動員されることとなっていました。
当初、軍隊は国内の内乱や暴動を鎮圧することに主眼が置かれました。しかし1877年の西南戦争終結後、1880年代には清との対立が深まったのと並行して、次第に外国との戦争に備えた編成へと変化していくこととなります。
- 富国強兵とは、幕末から明治にかけて、欧米列強と対等になるため日本が掲げたスローガンである
- 代表的な政策には「税制改革」「殖産興業」「学制の公布」「徴兵令の公布」がある
2章:富国強兵政策の成立と影響
さて、2章では先に取り上げた政策がどのように展開され、その後にどのような影響を与えたのか解説します。
2-1:税制改革がもたらした影響
先に記したように、1873年に「地租改正条例」が公布されたのと前後して、全国各地で土地の測量事業(地租改正事業)が行われました。事業は農民たちの協力を得ながら急ピッチで進められ、1881年には全国の測量をほぼ完了しています。
しかし政府は財源確保のため、実際の収穫高を無視して一方的に地価を設定し、農民たちに押し付けようとしました。そのためこれに反発した農民たちは、各地で「地租改正反対一揆」を起こしています。
- とくに地価の算定が進められた1875年から1877年は大規模な反対一揆が相次いだ
- 1876年に三重県で生じた「伊勢暴動」や茨城県で生じた「真壁騒動」は、代表的な地租改正反対一揆として有名である
これらの強硬な反発を受けて、政府は1877年に地租を3パーセントから2.5パーセントに引き下げざるを得ませんでした。前掲の牧原によれば、「最終的に江戸時代より増税になったのは、東京・埼玉・岩手の三府県だけだった」6『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』152頁ようです。
地租引き下げの実現後も、農民たちの地租引き下げの要求は続きました。政治への関心を高めた農民たちは「自由民権運動」に合流し、農民たちが主体となったの民権運動は「豪農民権」と呼ばれるようになっていきます。
※自由民権運動に関しては以下の記事を参照ください。
→【自由民権運動とは】背景・影響・板垣退助の役割をわかりやすく解説
このように税制改革は富国強兵だけでなく、日本の政治運動にも大きな影響を与えることとなったのです。
2-2:殖産興業がもたらした影響
先に記したように、政府は富岡製糸場のように官営の鉱山や工場を開設して工業化を目指しました。これらの官営工場は「官営模範工場」と呼ばれ、工員たちも比較的恵まれた待遇を受けていたと言われます。
しかしその後、1877年に勃発した西南戦争の影響で財政難に陥った政府は、次第に官営工場の経営に窮するようになっていきます。そこで政府は、次のような施策を打ち出します。
1880年に「工場払下概則」を定め、軍需工場を除く官営工場や鉱山を民間に払い下げることを決定した
- 政府は払い下げによって、支出削減と民業の育成を図った
- ただしその際政府は、三井や三菱などの特定の商人に工場等を払い下げている
- その要因として払い下げの条件が厳しかったことも挙げられるが、これらの商人が政府首脳部と癒着していたことが指摘されている
- これらの政府首脳部と結びつきが強い商人たちは、「政商」と呼ばれていた
政商への払い下げは当時から批判されており、しばしば政治問題に発展しています。
たとえば、1881年、薩摩藩出身の開拓使長官黒田清隆が、開拓使所有の官有物を薩摩藩出身の商人五代友厚に格安で払い下げようとしたことが発覚しました。この出来事は「北海道開拓使官有物払い下げ事件」と呼ばれており、自由民権運動に参加した人々を中心に激しい反発が生じています。
この時、政府は民権派の反発を抑えるために、五代への払い下げを中止したほか、「国会開設の勅諭」を発して1890年の国会開設を約束しています。このように払い下げに対する反発は、国会開設の大きな転機をもたらすことにつながったのです。
一方で、その後も政商たちへの払い下げは続き、政商は経営規模を拡大させ続けました。そして規模を拡大した政商たちは、1910年代前後から「財閥」と呼ばれるようになっていきます。
財閥の中でも三井・三菱・住友・安田は「四大財閥」と呼ばれ、持株会社を中心に「コンチェルン」と呼ばれる形態をとり、金融・産業・商業取引を統一的に支配するようになっています。こうして日本経済は、財閥によって独占されるようになりました。
※4大財閥に関してはこちらの記事→【4大財閥とは】歴史から現在までの流れをわかりやすく解説
財閥の拡大は日本の経済発展をもたらした一方で、財閥による独占支配は貧富の格差を生み出しました。そのため日本の国内市場は拡大せず、これが日本の対外進出を後押しする大きな要因になったと考えられています。
2-3:学制・徴兵制がもたらした影響
学制や徴兵令の公布により、人々は学校教育や軍隊生活に従事するようになりました。庶民にとっては負担であり、各地で「学制反対一揆」や「徴兵反対一揆」が発生する事態を招いています。
一方で学校教育や軍隊生活は、人々の意識や習慣を大きく変えていくこととなりました。ここでは主に前掲の牧原憲夫『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』に依拠しながら、それぞれを通じて人々の意識が変化した様子を確認していきます。
(2023/08/08 13:10:12時点 Amazon調べ-詳細)
2-3-1 : 学校教育を通じて変化した意識
先に紹介したように、明治以前に教育を担った寺子屋や筆書所では個別指導が行われ、教師は子どもの理解度に応じて「分かるまで教える」のが一般的でした。しかしこの方式では、一定の能力を身に付けた人材を大量に用意することは困難でした。
そのため、個別指導から一斉授業に方針が改められ、あわせて生徒の理解度を確認するために試験が行われるようになっています。
たとえば、小学校でも、月例試験や半年ごとに行われる進級試験、そして数校合同で行われる卒業試験など各種試験が行われており、牧原は教室が「相対評価と選別の場」になったと述べています。
もちろん、明治以前の日本で試験が行われていなかったわけではありません。たとえば、以下のような事例を提示することができます。
- 主に、武士の指定が入学した藩校や儒学者の広瀬淡窓が開いた「咸宜園」では、試験による席次の移動や等級別カリキュラムが導入されている
- しかし、これらの教育機関は、学問への志がある人物が入校する場所であった
- つまり、庶民の子どもが入校する小学校でも同様の試験が行われたのは、明治以前には見られない光景であった
試験は多くの落第者を生み出し、半数以上の子どもたちが中途で退学する事態にもなっています。しかしその後も政府は、若干の修正を加えつつも試験を中心とする一斉授業を続けていきました。
その理由について、牧原は次のようにまとめています7牧原憲夫『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』134頁。
一定の教育水準を確保するには統一的で厳格な試験が必要だった。何より、今や自由経済、弱肉強食の社会である。〔中略〕試験という難関を突破する意欲と実力のある者こそが、<一身独立><立身出世>に値する人間なのだということを、子供や親に痛感させる必要があった。
それだけでなかった。始業時間の10分前に登校し〔中略〕細かい時間割に区分された授業をじっと座って辛抱強く受けつづける、そうした身体-精神規律を身に付けた者こそが文明社会に適合的な人間であり、近代的な組織体、とりわけ軍隊や工場が求めたものだった。試験は学習の成果のみならず、そうした規律を身に付けたかどうかを点検する場でもあった。
牧原が述べるように、試験を通じて人々は競争社会に適合するようになっていきました。ほかにも時間遵守など、近代的な組織で必要となるさまざまな規律を身に付けるようにもなっていったのです。
ちなみに、学校教育のこのような側面はフーコーの権力論でもおなじみです。フーコーの権力論に関しては、以下の記事を参照ください。
2-3-2 : 軍隊生活を通じて変化した意識
学校教育と同じように、軍隊での経験も、人々の意識や習慣に大きな変化をもたらしています。
- 兵営に入営した若者たちは洋風建築の兵舎で暮らし、起床ラッパなどの合図に合わせて決められた日課をこなさなくてはならなかった
- 時間にあわせて行動するだけでなく、軍隊では整理・整頓・清潔について細かく規定されており、兵士たちは軍隊での生活を通じてこれらの規律を身に付けていった
現在一般に、日本人は時間に厳格であると言われることがあります。しかし幕末に来日したオランダのW.カッティンディーケは『長崎海軍伝習所の日々 日本滞在日記抄』の中で、日本人を「日本人の悠長さといったら呆れるくらいだ」と評しています。
そして、彼はその具体例として、商品の納期をまったく守らない職人や雑談ばかりで仕事を進めようとしない人々の姿を記しています。
このように「時間に厳格な日本人」像は明治以前には必ずしも当てはまらず、こうした規律は学校教育や軍隊生活を通じ、人々に定着したものと考えられています。
また意外な所では、歩き方も軍隊生活を通じて変化しています。江戸時代までは腕を振って歩く習慣がなく、多くの人々が「ナンバ」と呼ばれる右足と右肩を同時に出す歩き方をしていたと言われます。
※「ナンバ」について、同じ方の手足を同時に出す歩き方であると言われることが多いですが、身体をひねらない、腕を振らない、というのが本来の特徴であったという説もあります。
軍隊では西洋流の歩き方で行進の訓練が行われており、このような訓練を通じて大正・昭和期まで時間をかけながら、歩き方も変化していきました。
※身体技法に関しては、ハビトゥスの記事で学術的な議論に触れています。→【ハビトゥスとはなにか】その意味から具体例までわかりやすく解説
3年の兵役を終えて郷里に帰った兵士たちは、これらの近代的な習慣を農村にもたらす役割を果たすこととなります。もっとも前掲の牧原によれば、
3年の兵役を終えて戻ったとき、彼ら〔注.軍隊生活を通じて時間遵守・整理整頓・清潔を身に付けた若者たち〕と村人の落差は大きく、「不潔だ」「だらしない」といった苛立ちと、「兵隊帰りは生意気だ」といった反発が交差し、小さなトラブルが絶えなかった。
そうです8牧原憲夫『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』145頁。
このように学校生活や軍隊生活は、人々の意識や習慣を近代社会に適合したものへと作りかえていきました。このような人材が作られていったことが、日本の近代化を推進する原動力となったのです。
2-4:富国強兵がもたらしたもの
ここまで税制改革、殖産興業、学制、徴兵制を中心に、富国強兵のために実施された具体的な政策を確認してきました。
政府にとって富国強兵は、欧米列強と肩を並べることを目指したスローガンでした。しかしそのためには社会全般の大きな変革が必要であり、富国挙兵の名の下にさまざまな政策が展開されています。
その結果、
- 富国強兵は表層的な変化に留まらず、日本人の意識や感覚のような深層的な面でも大きな変化をもたらした
- ほかにも経済や政治などの面でも、その後につながるさまざまな変化が生じた
こととなります。
このことから富国強兵策の展開は、今日の日本社会の原型が形成されるきっかけとなる大きな変化と考えられているのです。
- 財閥拡大の結果、日本の国内市場は拡大せず、これが日本の対外進出を後押しする大きな要因になった
- 学校教育や軍隊生活をとおして、近代的な組織で必要となるさまざまな規律を身に付けるようにもなっていった
3章:富国強兵について学べるおすすめ本
富国強兵について理解を深めることができたでしょうか?
富国強兵は、さまざまな社会理論と密接に関係しています。他の理論と関連づけて学習することで、社会をより深く洞察できるようになるでしょう。ぜひチャレンジしてみてください。
オススメ度★★★ 牧原憲夫『日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』(小学館)
本文中でも取り上げた一冊です。民衆の立場から、富国強兵の過程で行われた諸政策の影響をまとめています。近代国家の形成が、人々の生活をどのように変化させたのか理解することができるでしょう。
(2023/08/08 13:10:12時点 Amazon調べ-詳細)
オススメ度★★★ 坂野潤治、大野健一『明治維新 1858-1881』(講談社)
本文中でも指摘した通り、富国強兵は幕末から唱えられ続けた概念です。本作品は明治と幕末の連続性に着目し、「柔構造」という概念を用いて日本の近代化過程を分析します。富国強兵についても柔構造の観点から分析がなされており、富国強兵の内実について興味深い知見を得ることができるでしょう。
(2026/01/29 19:37:41時点 Amazon調べ-詳細)
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 富国強兵とは、幕末から明治にかけて、欧米列強と対等になるため日本が掲げたスローガンである
- 代表的な政策には「税制改革」「殖産興業」「学制の公布」「徴兵令の公布」がある
- 学校教育や軍隊生活をとおして、近代的な組織で必要となるさまざまな規律を身に付けるようにもなっていった
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら