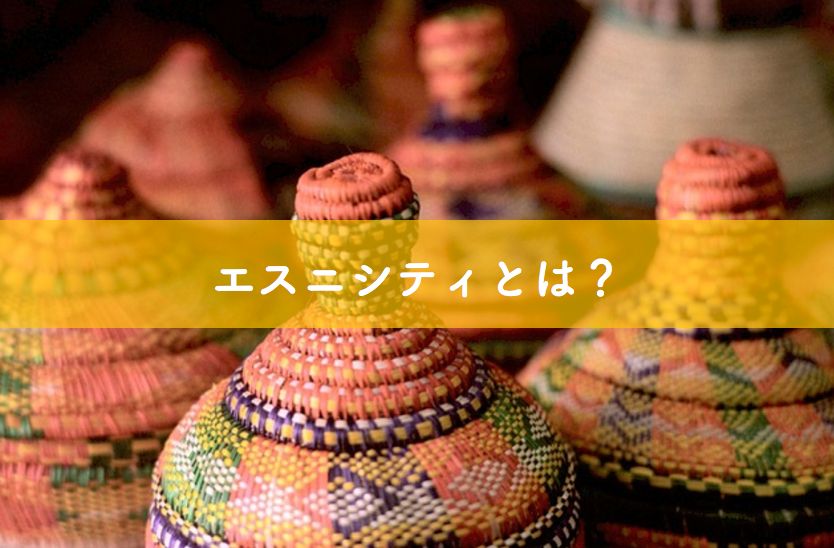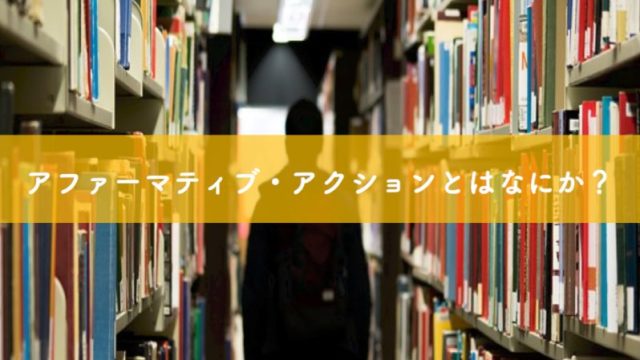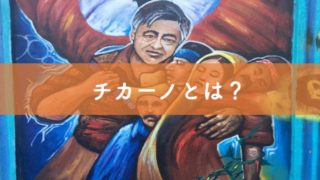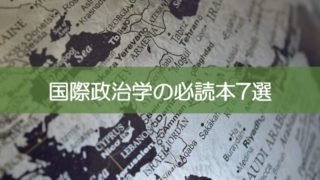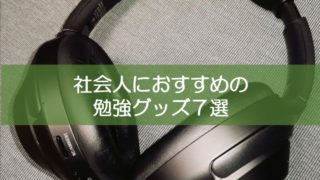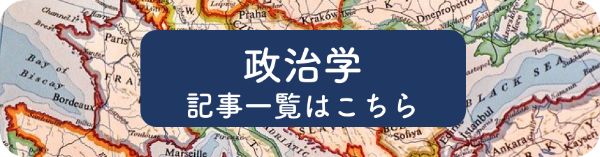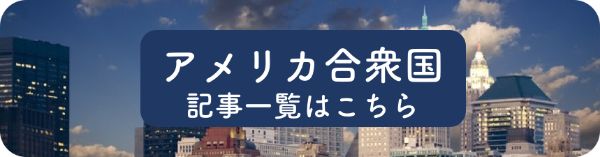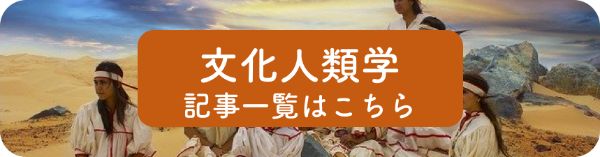エスニシティ(ethnicity)とは、エスニック集団が表す心理的・社会的な現象です1『文化人類学20の理論』(2006)を参照。
しかし、「エスニシティ」「エスニック」「民族」など似たような言葉ばかりで混乱しているのではないでしょうか。
世界を理解するための切り口は多様にありますが、エスニシティはもっとも頻繁に使われる切り口の一つです。
エスニシティを理解することで、たとえば、ヨーロッパやアメリカの移民問題、日本の外国人労働者問題を解決するきっかけをつかめるからです。
そこで、この記事では、
- エスニシティの定義
- エスニシティが誕生した歴史
- エスニシティへの批判
- エスニシティを知るための書籍リスト
をそれぞれ順番に解説します。
興味のある章からで構いませんので、エスニシティをしっかり理解しましょう。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:エスニシティとはなにか?
それではまず、エスニシティの意味を解説します。エスニシティが誕生した歴史を知りたい方は、2章から読み進んでください。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注2ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1: エスニシティの定義とは?
ではさっそく、エスニシティの定義を解説します。繰り返すことになりますが、エスニシティとは、以下の意味を指します。
エスニック集団ないしはその構成員が表す心理的・社会的現象3『文化人類学20の理論』(2006)を参照
そして、エスニック集団とは、ある地域に生活する社会的な実体を指します。
しかし、エスニシティとは、
こうしたエスニック集団が他のエスニック集団との相互作用のなかで意識的あるいは無意識的に表出する現象
を指します。なぜ他のエスニック集団の存在と交流が重要なんでしょうか?
1-2: 国民国家とエスニシティの関係
そもそも、エスニシティは「ある国家には多くのエスニック集団が存在する」という出発点があります。つまり、他にも似たようなエスニック集団が同じ国家に多数いることが前提なのです。
エスニック集団とは「ethnic groups」の訳語で、この言葉を民族集団と訳す人も多いです。複数形の「集団」であるのは、同種の集団が多くいるという前提のためです。
つまり、エスニシティとは、
- エスニック集団という社会的実体を前提としていること
- そのエスニック集団は単一ではなく、国民国家を構成する多数のエスニック集団の存在を前提としていること
- エスニック集団の成員が境界を越えて交流するなかで、自己と他者の基準をつけるために表れてくる心的・社会的現象
であるといえるでしょう。
「民族」といった静的な言葉とは異なり、エスニシティとはエスニック集団の相互交渉から生まれる動的な現象だということを理解しましょう。
※エスニック集団、民族、国民の違いや定義について、詳しくは以下の記事で解説しています。→【ナショナリズム・国民国家とは】成立過程から問題までわかりやすく解説
これまで解説したエスニシティの概念は、綾部恒雄(編)『文化人類学20の理論』(弘文堂)で解説されています。文化人類学の研究から練り上げられたエスニシティという概念がわかりやすく説明されているのでオススメです。
- エスニシティとは、エスニック集団が表す心理的・社会的な現象である4『文化人類学20の理論』(2006)を参照
- 「民族」といった静的な言葉とは異なり、エスニシティとはエスニック集団の相互交渉から生まれる動的な現象である
2章:エスニシティが生まれた歴史
ここでは、エスニシティ概念がいつなぜ生まれたのか?を解説します。エスニシティの定義は比較的理解しやすいものですが、この概念が発生した歴史は複雑です。
エスニシティ概念の歴史を知るためには、
- ヨーロッパからの白人移民の歴史
- アメリカ合衆国での人種主義の歴史
を理解することが不可欠です。
ですので、まず簡潔にヨーロッパからの白人移民の歴史に触れたいと思います。
2-1: ヨーロッパからの移民:アメリカ合衆国の白人のエスニック集団
さっそく、アメリカ合衆国のエスニック集団形成の事例を紹介したいと思います(ここでは、黒人やチカーノ、アジア系といったエスニック集団の事例には触れません)。
ヨーロッパからの移民を大雑把に分類すると、以下の集団がいます。
- 1776年にイギリスから独立して以来の、アングロサクソン系やドイツ系の初期移民
- 北欧(スカンジナビア三国)、南欧(イタリア・ギリシャ)、東欧(ロシア・ポーランド)などの移民
- ロシア皇帝の反ユダヤ政策から逃れてきたユダヤ人移民
- ジャガイモ飢饉に見舞われたアイルランド人移民
ヨーロッパから移民は言語や宗教をもちこんだ人びとでしたが、三世代を経ることによって次第にエスニック集団と呼ばれるようになりました。
1960年代までにエスニック集団間の通婚が進み、アメリカ合衆国に同化すると考えられていました。しかし、現在でもハイフン付きアメリカ人(たとえば、Irish-American)があるように、エスニック集団間の特徴は色濃く残っています。
■ 白人移民の同化を説明する理論としてのエスニシティ
数いるヨーロッパからの移民で一番重要だったのは、19世紀後半の東・西ヨーロッパからの白人移民です(彼らは「新移民」と呼ばれました)。
なぜならば、そもそもエスニシティ概念は、
- 白人新移民がアメリカ合衆国の主流文化を獲得することによって同化する過程を説明するもの
- そして同化していきつつも、エスニック集団の成員によって内側から文化的差異を説明するもの
として誕生したからです。
なぜそのような誕生が必要だったのか?というと、「科学的な」人種主義がパワーをもつ時代に、文化の獲得と多様性を強調するリベラルな理論が必要とされたためです。
ここでようやく、人種主義とエスニシティが重要になります。両者の関係をみていきましょう。
2-2: 人種主義とエスニシティ
20世紀初頭の人種主義は、生物学的な要素に基づき人種の優劣を決定していました。
※人種主義について詳しくは、次の記事を参照ください。

19世紀後半の東・西ヨーロッパからの白人移民も人種主義の例外ではありません。当初、彼らは「白人」と考えられていませんでしたので、人種主義の対象になっていました。
そのような人種主義が蔓延する20世紀初頭のアメリカ合衆国で、エスニシティは生物学的決定論としての人種に対抗するようなリベラルな思想として機能しました。
加えて、人種主義はある集団に外部からカテゴリー化するのに対して、エスニシティは、さまざま形態のアイデンティティをその集団の成員自ら決めるという大変リベラルなものでした。
そして、東・西ヨーロッパからの白人移民が主流文化を獲得していくという説明は成功を収めます。
- 成功を収めた証拠に、第二次世界大戦後以降は「人種」という概念や用語そのものを解消し、「エスニシティ」に代替する動きが出現
- この動きは人類学者のフランツ・ボアズの学生が中心となって、1950年代から1960年代にかけて提唱されたもの
- 1950年のユネスコによる「人種に関する声明」では、「人種」を「エスニック集団」に代替するかしないかで大きな議論に発展
エスニシティは、リベラルな思想であるとわかると思います。
これまで内容をまとめると、エスニシティ概念の歴史とは、
- 主流文化を学習していく過程を意味するものとして出現したこと
- 東・西ヨーロッパからの白人移民の同化がモデルであったこと
- 人種主義に対抗するリベラルな思想であったこと
- 集団の差異はその集団の構成員が決定すること
といったといえるでしょう。
ここまで来ると、エスニシティはエスニック集団の動的な心的・社会的現象という定義がしっくりくるのではないでしょうか?
エスニシティの歴史は『Racial Formation in the United States』で学ぶことができます。英語自体はそれほど難しくありませんので、ぜひ挑戦してみてください。
- エスニシティ概念は、白人新移民がアメリカ合衆国の主流文化を獲得することによって同化する過程を説明するものであった
3章:エスニシティへの批判と今後の展望
ここからは、エスニシティへの批判と将来的な展望を解説します。エスニシティに対してなされた批判を理解することで、今後の展望が開けてくると思います。
3-1: エスニシティへの批判
まず、エスニシティに対してなされた批判を紹介しましょう。
エスニシティは、
歴史的・文化的に構築されたという主張するが、場所と集団の起源に強く結びついていること
が指摘されました。この点をわかりやすく解説します。
人種主義が批判されるのは、生物学的な要素から人間の行動を説明をするからです。つまり、人種が人間の本質的な能力を決定するという考え方が批判の対象となります。
その一方で、
エスニシティは文化的な要素(共通の歴史、慣習、言語)に基礎を置き、その集団内部の構成員がそれらの要素を獲得してく、というリベラルな思想に見えます。
しかしながら、エスニシティの根底は、血縁関係や共通の遺産という超越的(本質的)な要素がないだろうか?と指摘されます。それは本質的な人種主義とあまり変わらないと。
エスニシティ概念が乗り越えるべき点とは、
- エスニシティはある共通の歴史と共有された文化的コードが文化的アイデンティティを決定しているのではないか?
- エスニシティは単一の人々としての私たちに安定した、不変の、継続的な認識的枠組みと意味を提供しているのではないか?
といったものでした。
たしかに、遠い過去と繋がるイメージはエスニック集団に想像上の一貫性を与えます。そのようなイメージによって形成される集団は、排外的で本質的な可能性があります。
3-2: エスニシティの今後の展望
すると、今後私たちはどのようにエスニシティを捉えるべきなのでしょうか?
この問いに答えはありませんが、私たちがすべきなのは、本質的ではないエスニック集団を想像することではないでしょうか?
カルチュラルスタディーズのスチュワート・ホールは、次のように言いました。少し長いですが、彼の言葉を記載します。
文化的アイデンティティとは「あるもの(being)」ではなく、「なるもの(becoming)」なのである。つまり、この文化的アイデンティティは本質化された過去のようなものに永続的に固定化されるというものではなく、歴史、文化、権力の継続的な「戯れ(play)」に従わなければならない。アイデンティティとは、私たちの自意識を永遠に保証しうる過去の単なる「再生」に根拠づけられるものではなく、私たちが過去の語りによって定位され(positioned)、その内部に私たち自身を定位する様々な様式に対して与えられる名前である。(『現代思想臨時増刊号 スチュワート・ホール』(2014)を参照)
いかがでしょうか?
エスニシティとは歴史的な場所や集団に固定化された「あるもの」ではなく、エスニック集団が歴史的状況によって実際に「なってしまったもの」、と認識する必要があるのです。
エスニシティを本質化せずに、未来に向けたアイデンティティの表出として捉えるべきではないでしょうか?
Sponsored Link
4章:エスニシティを知るための書籍リスト
最後に、「エスニシティをもっと学びたい」という方のための書籍リストを紹介します。ここで紹介する本に基づいて、この記事は書かれています。
まず、何よりも文化人類学という学問自体に興味をもった場合は、こちら記事を参照ください。さまざまな書籍の良い点と悪い点を解説しながら、紹介しています。
https://liberal-arts-guide.com/cultural-anthropology-books/
綾部恒雄(編)『文化人類学20の理論』(弘文堂)
文化人類学のさまざまな理論を学べる最高の入門書です。エスニシティに関する理論も当然あります。
スチュワート・ホール『現代思想』(青土社)
2014年に創刊されたスチュワートホールの臨時特集。エスニシティはもちろん、さまざまな文化理論を提唱した彼の論考を学ぶことができます。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後に、この記事の要点をまとめます。
- エスニシティとはエスニック集団が表す心理的・社会的な現象
- エスニシティは、白人新移民がアメリカ合衆国の主流文化を獲得することによって同化する過程を説明するものとして登場
- エスニシティを本質化せずに、未来に向けたアイデンティティの表出として捉えるべき必要性あり
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら