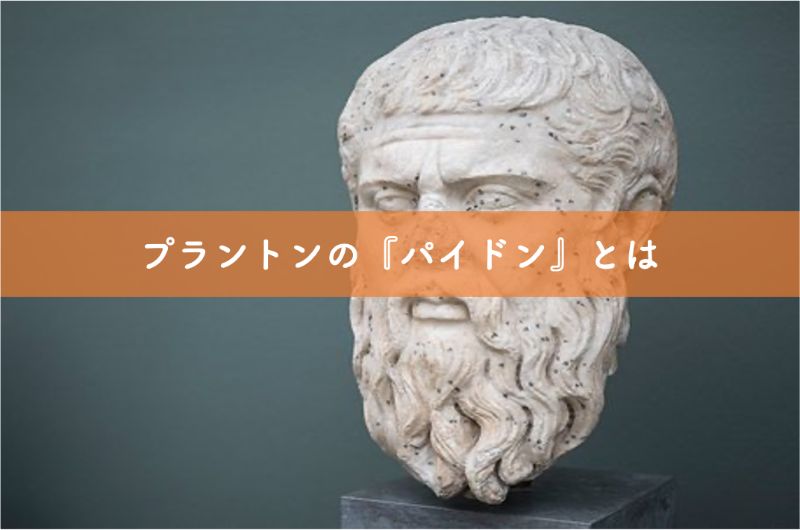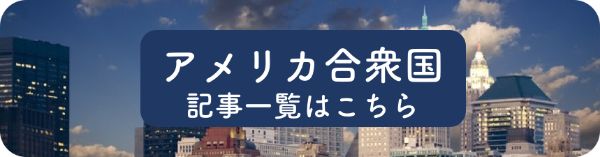プラトンの『パイドン』とは、ソクラテスが最期を迎えるという劇的な場面設定において魂の不死を哲学的に論じた書物です。イデア論や想起説というプラトンの重要な思想も登場します。
『パイドン』には、「私」とは何かということを出発点にして人間とは何かについて考えるヒントがあります。そのため、プラトンの魂論は、彼の「人間学」の重要な部分だと言えるかもしれません。
この記事では、
- プラトンの『パイドン』の時代背景
- プラトンの『パイドン』の要約
- プラトンの『パイドン』の学術的議論
をそれぞれ解説していきます。
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら
1章:プラトンの『パイドン』とは
1章ではプラトンの『パイドン』について知っておきたい基本的なことを説明します。そのうえで、2章から『パイドン』の内容や専門的な議論を取りあげて『パイドン』をより深く読むための視点を提供します。
このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。
1-1:プラトンの『パイドン』の時代背景
古代ギリシアの哲学者プラトンの師であった哲学者ソクラテスは、民主政下のアテナイ(現在のアテネ)において、ギリシアの神々を信じず若者たちを堕落させているという訴えによって起こされた裁判により死刑判決を受けました。
その判決に従い、ソクラテスは紀元前399年に処刑されます。『パイドン』はソクラテスの処刑の日に行われた対話という設定で書かれています2納富信留「訳者まえがき」プラトン『パイドン――魂について』納富信留(訳)8–9頁、光文社。
1-2:プラトンの問題意識
『パイドン』には「魂について」という副題が伝統的にはつけられています。古代ギリシア哲学において魂は、生命原理であるのみならず感覚や思考という認識能力の原理としても想定されていました3内山勝利「プラトン」『哲学の歴史 第一巻:哲学の誕生【古代1】』内山勝利(編)476–478頁、中央公論新社。
現代でいえば「心」と呼ばれているものの機能と重なるところが多いです。『パイドン』におけるプラトンの問題意識は、そうした魂が不死であることを哲学的に証明することができるのかということです。
彼は実際にいくつかの証明を提示することになります。
- 魂の不死という考えは、それに賛同するかどうかは別にして古代ギリシアでも宗教的な文脈ではよく知られていたが、合理的な論証を行う哲学ではそれほど自明のものではなかった
- プラトンの弟子としても有名な古代ギリシアの哲学者アリストテレスでさえ、魂の不死であるかどうかという問題はほとんどの人間にとっては未解決であると考えていた4ミヒャエル・エルラー『知の教科書 プラトン』三嶋輝夫・田中伸司・高橋雅人・茶谷直人(訳)226–227頁、講談社
プラトンがどのような証明を提示しているのかについては後で詳しく取りあげます。
1-3:現代において『パイドン』を読む意義
魂の不死が哲学的に証明されると聞いて、多くの現代人は懐疑的な気持ちを抱くかもしれません。
19世紀の終わりから20世紀の半ばまで活躍した日本の哲学者である波多野精一も、初版が1943年に刊行された『時と永遠』において次のように述べています5波多野精一「時と永遠」『時と永遠 他八篇』98頁、岩波書店。
「不死性」はプラトン以来「霊魂」の不死性乃至不滅性として知られている。しかるにこの観念は、古き栄えある伝統にもかかわらず、甚しく意義の明瞭を欠き、殆ど学問的使用に耐えぬ嫌いがある。〔中略〕古来多くの偉大なる哲学者たちが好んで取扱った題目でありながら、霊魂不死説ほど説得力に乏しき教説は他に稀れであろう。
他方で、2019年に『パイドン』の新しい日本語訳を公刊した納富信留は、『パイドン』に現代的な意義を見出そうとしています。それは、「魂」を神話的に語られる実体として理解するのではなくて、「私自身」(つまり個々の人間の自我)の究極的なあり方を指すものとして理解するというものです6納富信留「解説」『パイドン』納富訳、271頁。
『パイドン』が問題として示そうとするのは、「魂」という名称で語られる曖昧で神話的な実体が、死後に肉体から離れて冥府で存在するというお伽話ではない。むしろ、「魂」という言葉によって初めて哲学として語られる私自身のあり方、いや「この私がある」とはどういうことかが、根本的な次元に遡って徹底的に問題化される。それは、現代にもはや問題にする余地がない古い謬見ではなく、現代でも解かれてはいない謎としての「私自身」、そして「私がある」という哲学的難問なのである。ここに問題の核心があり、これを黙過して死後の魂云々を語っても、意味はない。
このようにして、たしかに魂の不死という考えには一見すると容易には受け入れがたい側面があるものの、そこには全く哲学的な意義がないと言ってしまうのは言い過ぎかもしれません。
むしろそこには、「私」とは何かということを出発点にして人間とは何かについて考えるヒントがあるように思われます。プラトンの魂論は彼の「人間学」の重要な部分だと言えるかもしれません。
- プラトンの『パイドン』とは、ソクラテスが最期を迎えるという劇的な場面設定において魂の不死を哲学的に論じた書物である
- 『パイドン』には、「私」とは何かということを出発点にして人間とは何かについて考えるヒントがある
2章:プラトンの『パイドン』の要約
2章では、『パイドン』の重要な部分として、次の三つの部分をみていきます。
- 哲学者のあり方について
- 魂の不死を論証する三つの証明
- 魂の不死性に関する第四の証明の提示
2-1:①哲学者のあり方について
『パイドン』は架空の対話編で構成されています。死刑当日を迎えたソクラテスの周りには弟子や知人が集まっています。そのなかでソクラテスは、一方では自殺禁止論を主張するにもかかわらず、彼自身は喜んで死刑を受け入れていることを問題視されます。
ソクラテスの自殺禁止論
- ソクラテスによる自殺禁止論は、「神がなんらかの必然の定めをお送りになる前に自分を殺してはならない」7ソクラテスによる自殺禁止論という言葉に集約されている
- 個々の人間の定められた運命のようなものが神による定めとして表現されていて、そうした運命に反して自らの生死を決めることが禁止されている
- ソクラテスは、自分が死刑判決を受け入れて死刑に臨もうとしていることは、むしろそうした運命に従ったことだと考えている
しかしながら、ソクラテスの対話相手の一人であるケベスは、そうしたソクラテスの態度には納得できずにさらなる説明を求めます。そこでソクラテスは、哲学とは「死の練習」であるという考えを述べることになります8同上、56頁。
正しく知を愛し求める哲学者たちは、死にゆくことを練習しているのであり、また、人間の中でとりわけ彼らにとっては、死んでいる状態はすこしも恐ろしくないものなのだ。
ここで注意したいのは、「死」ということでプラトンは何を言おうとしているかです。まず、彼は魂と肉体が分離することを「死」と呼んでいます。
次に、そうした死によって人間は無になるのではなくて、「魂が肉体から分離されて、それ自体としてある」9同上、43頁という状態になることが意味されています。
言い換えるならば、プラトンはそうした「死」によって人間ははじめて純粋に自分自身になると考えており、そのように努力することが哲学者の仕事だと考えています。
そして、魂が肉体とは別に存在できるということは、続く箇所では魂の不死性として改めて論じられることになります。
魂と肉体が分離するという説明はたしかに、現代の私たちにとっては容易に理解するのが困難な(あるいは理解するのが不可能な)ことかもしれません。しかし、ここではプラトンが何を言おうとしているかということに注目するのがいいです。
- 彼の考えによれば、人間が肉体をもった状態はさまざまな欲望に惑わされることが多い一方で、魂(特に知性的な能力としての魂)はそうした欲望とは別のものを目指すことができる
- より具体的には、正しさ、美しさ、善さといったことそのものについて、人間の知性は知ることを求めることができる
現代の私たちであっても、何が正しいことであり何が善いことであるのかということについて、日々の生活のなかで悩む場面が存在します。
そのようなときに、正しさや善さということについてきちんとしたことを知りたいという思いが少しでもあるなら、その人はすでに正や善とは何なのかという問いを追求し始めています。
「イデア」とは、そうした問いの答えになるようなもののことだと差し当たりは思ってもかまいません。魂と肉体の分離という「死」は、少なくともプラトンにとって、イデアを求める哲学者にとって理想的な状態を表していると言えるかもしれません。
※イデア論に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。→【プラトンの『国家』とは】要約して内容をわかりやすく解説
2-2:②魂の不死を論証する三つの証明
次にプラトンは、魂の不死に関する三つの証明を提示します。それはそれぞれ「相互生成論」「想起説」「類似性」による議論にもとづくものです。ここでは三つの証明について簡単に見ていきます10エルラー『プラトン』、227–228頁。
2-2-1:相互生成論
第一の証明は、反対のものは反対のものから生まれるということから出発します。
たとえば、「より大きなものが生じる場合、以前にはより小さかったものから、後により大きなものになるのが必然」11『パイドン』納富訳、68頁とプラトンは言っており、これに類似した事例を複数挙げていきます。
ところで、生と死は反対のもの同士です。そこからプラトンは、「生きている者から死んでいる者が生じているのと少しも劣らず、死んでいる者から生きている者が生じている」12同上、74頁という論理を駆使します。
そこからの帰結として、「死んでいる者の魂がどこかに存在していて、その魂がそこから再び生まれてくることは必然である」13同上、74頁というように、魂の不死が示されるにいたります。
この証明そのものは必ずしも納得のいくものではありませんが、ここで語られている魂の輪廻転生とも言うべきことが以降ではより具体化されて説明されることになります。
2-2-2:想起説
第二の証明は想起説にもとづくものです。この証明の大枠は、次の引用から窺うことができます14同上、78頁。
〔想起説とは――引用者注〕即ち、私たちにとって学びとはまさに想起にほかならないという説で、これに従えば、私たちが今想い出すことを、私たちはいつか過去の時にどこかで学んでしまっているというのが必然なのです。このことは、もし私たちにとって魂がこの人間の姿に生まれる以前にどこかで存在していたのでなければ、不可能なのです。従って、この点でも魂はどうやら不死のものであるようです。
プラトンの想起説はより詳しくは『メノン』という対話編で提出されているものですが、『パイドン』ではそれがイデア論と密接に関わるものであることが明示されます。
想起説によれば、私たちが何かを学ぶということはすでに知っているものを思い出す(すなわち想起する)ことにほかなりません。現代的に言いかえるなら、私たちの知識は生得的なものであるという主張でもあります。
こうした想起説に従うなら、以下の意味になります。
- 私たちはすでに善とは何かや美とは何かということについてもすでに知っていることになるが、これは私たちが実はイデアをすでに知っていて、思い出しさえすれば善や美の本質について把握することができるということを意味する
- そして、イデアを最初に見た時が、肉体と結合する前の魂だけの状態とされる
ここで、魂の不死性が要請されることになります。
2-2-3:類似性
第三の証明は、第二の証明におけるイデア論との関連をより突き止めたものです。
すなわち、人間の知性的な魂が見る対象としてのイデアが不滅のものであるのだから、そうした不滅のものを見る主体である魂も不滅のものであるという類似性が根拠とされます。
次の引用文は、この第三の証明だけではなくてプラトンの人間学を端的に示すものでもあります15同上、112頁。
一方で、神的で不死で知性的なもので、単一な相をなし、分解不可能で、つねに同じ仕方で同じものに即したあり方をするもの〔すなわちイデアのこと――引用者注〕、そのもの自体にもっとも似ているのは魂である。他方で、人間的で死すべきものであって、多くの相からなり非知性的で分解可能で、けっして同じものに即したあり方をすることがないもの、そのもの自体にもっとも似ているのは、今度は肉体である。
2-3:③魂の不死性に関する第四の証明の提示
魂の不死性に関する証明はまだ続き、『パイドン』の後半では第四の証明が提示されます。
というのもプラトンは、「『なにか美そのものがそれ自体としてあり、善や大や他のすべてもそのようになる』ということを基礎に定立する」16同上、112頁というようにしてイデア論を改めて議論の出発点として設定することにより、それと魂の不死性との関連を改めて論じようとするからです。
この証明について最後に確認します17エルラー『プラトン』、229–230頁。
始めにプラトンは、2や3という数を例にして、2と3はそれ自体では互いに反対の関係にあるものではないが、偶数と奇数という性質に注目すると対立関係があることに注目します。
2や3のイデア、あるいは偶数や奇数のイデアが前提されていますが、それだけではなくて、そうしたイデアを受容するものは対立関係にあるイデアを同時に受容することは不可能だとも言われています。
次にプラトンは、魂には生命原理としての側面があることに言及します。ところで、「生」というイデアと対立関係にあるのは「死」のイデアにほかなりません。
それゆえ、プラトンによれば、「生」のイデアを受容している魂は「生」と対立関係にある「死」のイデアを決して受容しないことになります。「死」と対立関係にあるものは「不死」にほかならないので、魂は不死であるとプラトンはあっさり結論することになります。
この証明は、現代の私たちから見ると何となく騙されているようにも思えてしまうかもしれません。しかし、哲学的に重要なのは、魂の本質に注目するならそれは「生」であるということが擁護されているということです。
- このように、或るものの本質的な側面に注目してそれがどのような存在であるかを論証するような種類の証明は「本体論的証明」ないし「存在論的証明」と呼ばれ、西洋哲学では神の存在証明として用いられることが多い20上枝美典『「神」という謎[第二版]―宗教哲学入門―』(世界思想社)、192–221頁
- それをプラトンが魂の不死性を証明するのに用いていることに敢えて意味を見出すなら、彼にとっては神学的な関心よりも人間学的な関心がより強かったと言うことができる
魂に関する哲学的な問いは、すべて人間に関する問いかけだとプラトンなら言うかもしれません。
- 哲学者のあり方について
- 魂の不死を論証する三つの証明
- 魂の不死性に関する第四の証明の提示
3章:プラトンの『パイドン』に関する学術的議論――ソクラテスの最後の言葉の意味
3章では、『パイドン』のなかでソクラテスの最後の言葉として語られている内容に関するいくつかの解釈を紹介することで、『パイドン』が全体としてはどのようなことを主張する哲学書だったのかについて考える視点を提供します。
ソクラテスの最後の言葉として語られているのは次のものです21『パイドン』納富訳、258頁。
クリトンよ、ぼくたちはアスクレピオスの神様に鶏をお供えする借りがある。君たちはお返しをして、配慮を怠らないでくれ。
クリトンという仲間の一人に語られたこの言葉について特に問題になるのは、ソクラテスが神様の一人にお返しをしてくれとお願いしているのは何を意味するのかということです22金山弥平「ソクラテスの最後の言葉」『西洋古典学研究』第62号、24–38頁。
ここでは、二つの解釈について見ていくことにします。
3-1:生という病からの癒しへの感謝
これは古くはニーチェ(『悦ばしき知識』)も採用していた伝統的な解釈で、現世における生からの解放に対してソクラテスが感謝を述べていると考えるものです。この解釈の強力な論者アレクサンダー・ネハマスは次のように述べています23Alexander Nehamas, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, University of California Press, p. 161。
肉体に対する『パイドン』の憎悪はとても強烈で激しいものであるので、魂が肉体のなかに囚われている時である生が病以外の何かだとプラトンは考えているのだと信じるのは難しいほどである。
ただし、こうしたいわば現世を否定的に捉える解釈に対しては批判も存在します。
たとえば、ある研究者は、ソクラテスはこの言葉を言った時点ではまだ生きていて身体から完全には解放されていないのだから、この時点で神様に感謝することについて疑問を呈しています24Glenn W. Most, “‘A Cock for Asclepius’,” The Classical Quarterly, Vol. 43, No. 1, pp. 96–111。
3-2:「言論嫌い」(ミソロゴス)からの癒しへの感謝
これは現代フランスの哲学者ミシェル・フーコー(『真理の勇気』)が採用していた解釈で、プラトンが自らの対話編で描いているような言葉による哲学的な探求を通じた問題解決を肯定的に評価するものでもあります。
『パイドン』ではそうした問題解決の方法を全く信頼しない人々が「言論嫌い」と呼ばれていました25納富信留『プラトンとの哲学 対話篇をよむ』(岩波書店)、81–84頁。
この解釈を採用する現代の研究者ジョージ・ルードブッシュは、以下のように述べて、こうしたミソロゴスからの脱却が最後の言葉でも意味されていると考えます26George Rudebusch, Socrates, Wiley-Blackwell, p. 198。
ソクラテスによれば、最も恐ろしい状態とはミソロジーという精神的な病、すなわち理性的に考えることへの不信と憎悪である
この解釈にもやはり批判は存在していて、たとえば、言論嫌いからの脱却はあくまで人間たちによって自力でなされたことで神様は関係ないという指摘があります27金山「ソクラテスの最後の言葉」、30–31頁。
他方で、納富信留はこの解釈について共感を示しています28納富「解説」『パイドン』納富訳、317–319頁。この解釈が万能でないのはたしかですが、それでも伝統的な解釈とは異なり、必ずしも現世を否定的に捉えることなしに『パイドン』で語られる哲学者のあり方や魂の不死を解釈できる点が魅力的かもしれません。
このように、魂の不死という話題が有名な『パイドン』ですが、それ以外にも哲学的に重要な部分がたくさんあります。それを味読するためにも、翻訳で構わないので一度は通読することをおすすめします。
Sponsored Link
4章:プラトンの『パイドン』に関するおすすめ本
プラトンの『パイドン』について理解が深まりましたか?
この記事で紹介した内容はあくまでもきっかけにすぎませんので、下記の書籍からさらに学びを深めてください。
神崎繁『魂(アニマ)への態度――古代から現代まで』(岩波書店)
古代ギリシア哲学の専門家が、魂をテーマにして古代のみならず中世や近代の西洋哲学にも話を拡張し、さらには近世の中国や日本における西洋的な魂論の受容についても論じた講義風の一般書です。プラトンの問題意識を広く捉え直すきっかけにもなります。
オスカー・クルマン『霊魂の不滅か死者の復活か――新約聖書の証言から』(日本キリスト教団出版局)
キリスト教の神学者が、魂の不死は古代ギリシア哲学が強調していたことで、新約聖書ではむしろ肉体の復活という考え方の方が強調されていることを論じた一般向けの書物です。魂の不死が宗教的な考え方にすぎないのかどうかについても再考するきっかけになります。
一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。
最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。
Amazonオーディブル無料体験の活用法・おすすめ書籍一覧はこちら
また、書籍を電子版で読むこともオススメします。
Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。
数百冊の書物に加えて、
- 「映画見放題」
- 「お急ぎ便の送料無料」
- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」
などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- プラトンの『パイドン』とは、ソクラテスが最期を迎えるという劇的な場面設定において魂の不死を哲学的に論じた書物である
- 『パイドン』には、「私」とは何かということを出発点にして人間とは何かについて考えるヒントがある
- ソクラテスの最後の言葉として、語られている内容に関して解釈がわかれている
このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。
ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら